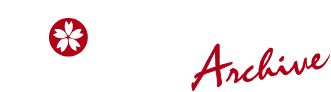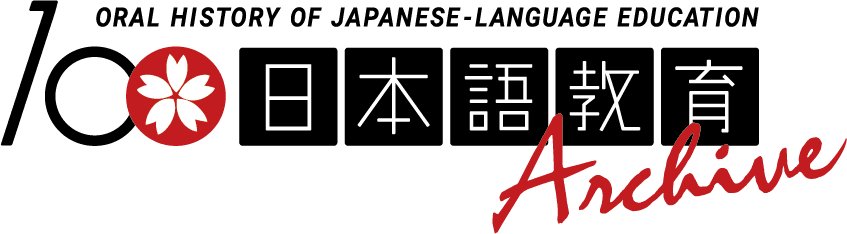02
EIKO YASHIRO
難民のこどもたちへ
屋代瑛子 Eiko Yashiro
1937年東京都杉並区生まれ。1960年東京女子大学文学部英米文学科卒業。1967年から1976年の間に、南米チリ及びペールに滞在。1979年より国際日本語普及協会で日本語教師となり、1980年から1994年までアジア福祉教育財団難民事業本部大和定住促進センターで年少者への日本語教育の講師を務める。
根本牧 Maki Nemoto
東京都出身。1972年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。銀行勤務を経て、ボランティアで日本語を教えるようになる。1979年朝日カルチャーセンター日本語教師養成講座修了後、1980年から1988年まで、アジア福祉教育財団難民事業本部大和定住促進センターで成人や年少者への日本語教育の講師を務める。1988年から1990年まで国際交流基金からインド・デリー大学に派遣され、その後、朝日カルチャーセンター日本語科、東京海洋大学、東洋大学などで日本語教育に携わる。
-

『ひろこさんのたのしいにほんご』
インドシナ難民のこどもたちのために作成された日本語初学者向けの総合教科書。年少者を対象とした教科書の草分けであり、国内外の日本語教育機関などで広く利用されている。語彙や文型の学習に加え、文字の学習にも力が入れられている。また、“九九”“足し算”などといった学校場面でよく使われる表現とその練習も充実しており、日本語を母語としないこどもが、日本での生活や学校に入ってゆくための支援にも効果的である。本文は、会話や手紙、物語など多彩で、イラストも充実しており、こどもたちが興味と関心を持って学習に取り組める内容となっている。副教材として、ワークブックや絵カード、指導書、音声Web教材などがある。戦後を代表する年少者向け日本語教科書といえる。
“ひろこさん”誕生エピソード

屋代氏と根本氏がアジア教育財団難民事業本部大和定住促進センター(以下、難民センター)で日本語を学習するこどもたちのために作り上げた教科書、『ひろこさんのたのしいにほんご』は、年少者向け日本語教科書の草分けとして名高く世界中で使用されているが、そもそもそのタイトルにもなっている“ひろこさん”は、どこからやって来たのか。
──いくつか候補があがったんです。私っておっちょこちょいの人だから。その時テレビで『おしん』をやっていたんですよ。主演の人が、田中裕子(たなかゆうこ)さんという。それを私は「たなかひろこ」だとずっと思い込んでいたの。難民のこどもたちも本当につらくてかわいそうな境遇にありましたから、それで「ああ、この子たちにも、なんとか日本という新しい環境でおしんみたいにしっかり生き抜いていってほしいな」と思って、私は「ひろこ」としたいと思ったんですね、そうしたら名前自体はなんか全然違って。いい加減なんですけど、込めた想いにはそういう強い気持ちがありました。
屋代氏が笑って語るように、日本語教育界の年少者向けベストセラー教科書の由来は思わぬ誤解に端を発するものであったが、辛い思いをして日本に来た難民のこどもたちが、なんとか日本語を学んで日本で生き抜いてほしいという切実な気持ちが込められたものであった。
日本語教育との出会い
──こども、苦手なんですよ。
根本氏は笑いながらそう言う。
──大学を卒業した時も、教える仕事とこども相手の仕事だけはやりたくないと思っていたのに、なぜか日本語教師と呼ばれる仕事に就きました。おとなだけでなく、こどもを対象にも教えましたし、まさか、こども向けの教科書を作ることになるとは思ってもみませんでした。
苦手だと言いつつ、こどもとの縁は大学時代から始まっていた。慶應義塾大学法学部に通っていた根本氏は、児童文化研究会で影絵劇などに取り組んだ。高校時代から影絵が好きだった、というのが理由だが、大学祭やこども会などでこどもたちに上演していたという。
大学卒業後は銀行に入行し、二年間務めた。銀行を辞めて根本氏が始めたのは、英語を教えることだった。
──そこでも、また、こどもなんですよ(笑)。
その時期の、こどもに英語を教えていた体験は、その後の教師人生で大きな助けになったという。同時に、民間の国際交流クラブのボランティアとして日本語を教える経験をした。これが日本語教育との出会いだった。しかしやってみたものの教え方が分からない。根本氏は朝日カルチャーセンターの日本語教師養成コースへ通い、ノウハウを学んだ。
初めて学んだ日本語の教え方は、根本氏にとって驚きだった。
──全て新鮮でしたね。文型なんかも、日本語のいわゆる国語文法ってなんか分かりにくいですよね。外国人に教える文法っていうのは、なんて分かりやすいんだろうと思って。
一年間の講習を経て、日本語教師となった根本氏は、同期の修了生たちと教える現場を探し始めた。
──ジャパンタイムズに新聞広告を出して、日本語を教えますとかいうのを出したりしたけど、何も反応はありませんでした。
当時はまだまだ日本語教育は発展途上、教えるための環境など整ってはいなかった。
やがて、朝日カルチャーセンターから、難民センターでの仕事を紹介された。
──ちゃんとしたところですし、なんかやりがいがあるんじゃないかと思って、ぜひ応募してみようと思って応募したんですね。仕事もしたいし。
本格的な日本語教育の現場に踏み出した、最初の一歩である。
インドシナ難民の定住受入れと日本語教育
8歳で終戦を経験し、戦後の混乱期に幼少期を過ごした屋代氏は、東京女子大学に進学し英米文学を学んだ。クラブ活動ではQGS(東京女子大学英語会)の副部長として、当時米軍家族が住んでいたワシントンハイツなどを訪問して、生の英会話を学んだ。また、米国人教師の指導のもとに英語劇の演出をしたり、夏休みには友人たちと山登りをしたり、冬休みにはスキーを楽しんだり、楽しく充実した学生生活を送った。
とミス・ローズ氏(右から二人目)と共に(中央が屋代氏)〔1958年・東京都杉並区善福寺〕-721x1024.jpg)
卒業後、結婚し、長男と次男と共に夫の仕事の都合でチリへ移住した。現地で5年を過ごし帰国した後、3年ほど日本に住み、次に2人のこどもと共に夫の仕事先のペルーに住むこととなった。日本語教育の存在すらも知らないままAJALT(国際日本語普及協会)の試験を受けた。
──ぺルーから帰ってきて、ある日、朝日新聞を読んでいたら、なんか国際日本語普及協会って西尾専務理事の話が出ていて、広告ではなく、そういう日本語教育の協会が設立されたという記事。それで、そこの会員になると生涯研究や勉強をしながら、会員を育てるって書いてあったんですね。なんだかさっぱり分からないけど、魅力を感じました。日本語教育のことは知りませんでしたが、細かいことは入ってから分かるだろうと、それで試験を受けたんですね。
3名の理事による面接では、「あなたはどんな日本語の教科書を知っていますか」と尋ねられ、屋代氏は驚いたという。
──もちろん、英語の勉強をしているから英語の教科書とか第二外国語でフランス語とかをやっていましたから、フランス語の初級用のテキストとかは知っていましたけどね。「え、日本語の教科書ってあるんですか」って言ったら、もうむこうも仰天して、なんかすごい変わった人が来たと思ったらしいんですね。
まさに右も左も分からず協会に入り、新人研修を目的とした週1回のミーティングに出席した。
──同期は9人だったんですけどね。他の人はもうすごい、みんないろんなところで勉強したり長沼スクールで教えていたり、国際交流基金で教えているとか、なんだかもうみんな経歴があった人で、私一人が何も知らないで入った人だったらしいんですね。それでわけ分からないけど、それでみんなも何かいろいろ教えてくれるんですけど、だいたい全然わけ分からない人が、そんな週1回ぐらい研修を受けても分かりませんよね。
そうこうしていると、難民センターでの仕事に新人が投入されることになり、屋代氏も選ばれた。日本で難民に対する門戸が大きく開かれた時期で、日本語教育についても力が入れられた。教科書は、『にほんごのきそ』が採用され、1日に50分授業を6コマ実施する授業計画が立てられた。
──それで始まって、いざ難民が来たらこどもがいたんですね。それまでは、「難民はおとな」ってイメージで頭の中がいっぱいだったんです。でも、本当に8歳とか6歳、いわゆる本当のこどもですね。親も殺されてしまっていないから、おとなクラスに入れられて座らされているんだけど、いくらなんでも6歳とか7歳が、1日6時間の授業を受けるんですよ。それはもう本当に気の毒で。お母さんが側にいれば、ある程度いいかもしれないけど、孤児で、非常にかわいそうでした。
見るに見かねて、こどもたちだけを取り出した特別クラスを作った。
──なんだか私、ボーッとしていたら「あなたこどもに向いているから」とか言われて。担当することになったんですね。
こどものための日本語教育

難民センターで、こどもを対象としたクラスに抜擢された屋代氏と根本氏であったが、まずもって直面したのは、“こどもたちに対しどのように日本語支援をすればいいのか”であった。インターナショナルスクールで用いられていた教科書や、英語を母語とするこども向けの教科書を取り寄せもしたが、ラオス、ベトナム、カンボジアのこどもたちには合わなかった。こどもたちにとっての定住促進、すなわち、日本の学校に通い義務教育が受けられるようになるまでの予備教育という目的に適う教材は存在しなかったのである。
また、好奇心旺盛でじっとしていないこどもたちに、一定の期間内にある程度の日本語力を習得させることは非常に難しかった。
──まだ学校にも行っていない子が多くて、鉛筆も握れない子もいました。だいたい机にじっと座っていることができない。やっぱり、こどもは飽きちゃいますからね。いかにして、飽きさせないで、勉強しているっていうことを感じさせないで、日本語を覚えてもらうかが勝負ですよね。おとなだと「これから日本語が分からないと日本で暮らしていけないから大変だ」っていう自覚が少しはあるかもしれませんけど、こどもにはそんなことはまだ分かりませんから。
教科書探しを続けたが、結局、こどもクラス用の適切なものは見つからなかった。おとなクラスと同様に、『にほんごのきそ』が用いられることになった。
──ところが、それを使ったってかわいそうですよね。小さい文字で何がなんだか、こどもたちには分かるわけないし。それで、「どう考えても、6歳の子に、この教科書では教えられません」って上司に伝えたんですね。そうしたら西尾専務理事が、「じゃあ、あなた好きなように教えなさい」って認めてくれたの。
屋代氏は同僚の根本氏の手助けも得ながら、自作教材を少しずつためていった。イラストをふんだんに取り入れたプリントを使って、授業を進めた。こどもたちを対象としたクラスのチーフとなった屋代氏は、センターの当時の主任からの要請で、毎日6時間の授業マニュアルを3ヶ月分作っていったという。

しかし、日本語指導のためのマニュアルは作れたものの、それだけでは、こどもたちの集中力は6時間も続かない。
──いろいろ私も考えて、他のこどもクラスと合同で朝は庭に出て体操をするようにしたんですよ。ラジオ体操第一。それで、「集まれ」とか「走れ」とか導入したりしました。担当した教師たちで知恵を出し合って。例えば、夏休みのラジオ体操みたいなカードを作って、はんこを押してあげたらいいとか思い付いた人もいて作ってくれた。体操の後に、縄跳びをすれば、跳んだ数を「いち、にい、さん、し」とかって教える。かけっこをすれば、「走ります」とかって一緒に走ったり。押しくらまんじゅうとか、いろいろやりましたよね、その日によって。疲れさせてあまり授業で暴れないように、ちょっと疲れたから静かにしようというところで授業させて(笑)。一日の最後の授業はもう飽きちゃっているだろうから、お絵描きの時間とかそういうのをやりましたね。掃除なんていうのも一緒にやって。おとなのクラスなんかは先生と一緒に掃除なんかしませんけども、私たちは掃除の時間とかいって一緒にやりました。
とにかく、こどもたちに寄り添い、こどもたちの興味や関心を喚起するアクティビティを設け、そこで、体を動かしながら自然にことばが学べるよう工夫がなされた。文型の導入時も、実際に公園へ行き、帰ってきてから「〜へ行きました」を教えた。公園ではいろいろな遊具の名前を遊びながら覚えられるようにもした。
同僚であった根本氏も体験型授業の大きな支えだったと、屋代氏は言う。学生時代に児童文化研究会に所属したり、こどもたちに英語を教えた経歴を持つ根本氏は、得意な絵を使ってフラッシュカードをたくさん作った。

──例えば、ねもっちゃん(根本氏)が自動車の絵を描いて、裏側に「じどうしゃ」って書いて。そういうのをなんか、どんどん出してくれたの。なんでこんな物使うのかしらと思ったけど、それで教えるとすごくこどもたちが喜んで、また、リピートも利くわけですよね。それで神経衰弱とか坊主めくりとかもできるじゃないですか。坊主めくりなんて先生は全然できないですけど、こどもって一生懸命やるから。「先生、これとこれだ」とか言って、教えてくれるんですね。そうやって、指示詞や伝達表現を覚えさせるっていう術を、ねもっちゃんは知っていたんですね。ゲームをやったり、イラストを描いたり、切ったり貼ったり、そういうことをして文字や表現の定着を図ったんですね。ただ口で、教師がペラペラと文型を教えてドリルをやらせても駄目なんです。
退屈させないように、こどもたちが少しでも体験としてことばを身につけることができるように、屋代氏と根本氏は同僚たちと共に日々体を張って創意工夫を重ねていった。
目の当たりにした悲惨な現実と希望
年少者を担当した屋代氏や根本氏のクラスには、栄養失調や貧困に苦しむ孤独なこどもたちがたくさんいた。
屋代氏は当時をこう回想する。
──本当にかわいそうでね。親はインテリで殺されちゃって、8歳とか6歳の時に。ほとんどの子は、受け入れ初期の子は母国で学校に行っていないですよ。本当に痩せていて、難民なんですよね。こんな小さくて栄養失調で、寒いのにパンツもはかないで。日本では心ある人たちからの古着の寄付がありますから、上に着る物はいっぱいあるんです。でも、下着とか肌着とかは古着でもないんです。生活の場もプレハブの6畳でね。そこに6〜7人が一緒にね。普通では寝られないじゃないですか、6畳では。だから布団を出して身を寄せ合いながら生活する。私は戦争を体験していますから、ある程度は分かりますよ。だけど、本当にかわいそうでした。
根本氏は、どうしても忘れられないことがあるという。
──担当していた女の子が父親に殺されてしまう事件がありました。お父さんが奥さんとこどもたちを殺してしまったと聞いて、すごいショックだったんです。心の優しいかわいらしい子だったのに。言葉では言い表せないくらい悲しかったです。
それから、クラスではラオス人やカンボジア人やベトナム人が共に学ぶのですけれど、やっぱり仲が良くないことがあるんですよね。こどもたちは、本当はわけも分からないのに「ラオス人ラオス人」、「カンボジア人、カンボジア人」とか、からかったりしているんですけど。そういうのって、きっと親世代の姿を見ているからだと思って、心が痛みました。
しかし、目の当たりにした悲惨な現実の中にも、こどもたちの目には強く光るものが宿っていたと根本氏はいう。
──すごい輝いているんですね。もうそれは日本人のこどもたちにはないもので。「ああ、なんて目が輝いているんだろう。」って思って。「ずっとこのままでいて!」っていうような気持ちでした。感受性が豊かですしね。いろいろな困難や不幸がある中でも、新しい環境に来てやっぱり「なんだろう」っていう好奇心を持つような感じで、キラキラしていた。とても印象的でした。

日本の学校を模した生活を共にする
こどもたちが日本の学校に通い義務教育を受け定住するための予備教育を行うというセンターの目的を果たすため、カリキュラムやシラバスが組まれた。屋代氏は留意していた点について次のように語る。
──センターの教室も日本の学校が再現されていますよね。教師としては、やっぱり生活を共にしながら、こどもたちが規律を学べる環境をつくることを意識しました。朝の挨拶と体操から、授業に掃除。そして食事も一緒に食堂で食べて。
根本氏は、小学校の教育内容や様子を把握するために直接学校へ取材に訪れることもあったという。
──センターでは3カ月間勉強しますけど、修了したあとはそのすぐ近くの小学校にみんな行くことになっているんですね。そこで、小学校にお邪魔させていただき、入学後の様子とか、必要な指導とかについて取材したりしました。
小学校側も、国際交流の機会として、センターのこどもたちと小学生との活動イベントを積極的に設けていた。大和市議会の記録には、その趣旨が座間茂俊教育長(当時)の発言としてのこされている。
──特別活動という領域におきましては、具体的な活動の場を設けまして、仲よく生きることや国際交流を図ることなどを実践的に学習する、そのような育成に努めるという場もあるわけであります。例えば南林間小学校が近くの難民定住促進センターの子供たちとさまざまな交流を図っていることなどは、その具体的な、実践的な活動の場であると思います。(昭和63年3月定例会、3月16日、02号)
教科書開発の発端と原動力
難民のこどもたちを対象とした日本語教育に従事するうちに、根本氏にはある思いがこみ上げてきた。
──しばらく教えていまして、こどもを教えてせっかくこんな貴重な体験をしたし、市販の教科書もないし、生徒たちにもやっぱり何か形がある物を作りたいなと思ったんですね。
その思いを同僚だった屋代氏に打ち明けると「あなたもそう考えていた?」と思わぬ賛同を得た。トントン拍子に話は進み、二人は教科書を作り始めた。
──わけも分からず、怖い物知らずで、だからできたんだと思います。
教科書開発の原動力はどこにあったのか。根本氏の原動力はこどもたちが希望を失わずに、たのしく学び、巣立って欲しいという想い。そして、屋代氏の原動力は、それに加え幼少期をチリで過ごした息子が言葉で苦労したという経験だ。
──センターで働く前に、長男が2歳半、次男が2ヶ月の頃、夫の仕事の都合でチリへ移住したんですね。現地で5年ほど生活しました。スペイン語圏の国で生活を始め、ことばで苦労をしました。「現地に行けば、こどもは自然に覚える」っていったって、現地では全然誰も近寄ってこないわけですよね。もちろん友達なんて2歳半でいないし。

そこで、長男が3歳になった時、5歳だと学校側に伝えカトリック付属小学校へ通わせた。3歳と5歳では、もちろん体の大きさも能力も違いすぎる。
──「tan chiquito(タン・チキート)」って、「なんて小さいんだろう日本人は」っていわれて、男子校だったんですけどね。そりゃそうですよね。便器なんかも3歳じゃ届かないんです。私、しょうがないから一緒に付いて行って、横に座ったりなんかして。
屋代氏も学校へ付き添い、一緒に授業を受けたりもした。長男は次第に話せるようになり、最後の一年は公立の小学校へ通わせた。いじめられながらも、学校から賞が授与されるほどに頑張った。そしていざ日本へ帰国すると、再び言葉の問題に直面した。
──日本の小学校1年生の終わりかな。今度は日本語が全然分からなくて苦労していました。2年生になってカタカナを習った時に、友達のお母さんが「ごめんなさい」って謝ってきたんです。なんのことかと思ったら、授業の課題で「知っている外人の名前を書きなさい」っていうのがあったそうなんですね。そしたら息子の名前の「ヤシロテツロウ」って周囲が書いたとかって(笑)。それで、日本語もわからないからものすごくいじめられて、ということが、こどもたち向けの教科書を作らないかと聞かれた時、突然よみがえったんですよ。息子と難民のこどもたちがなんか重なっちゃって。だから、こどもってかわいそうなんです。周りでなんとかしなきゃならないんです。
当時の長男の姿が、目の前にいる難民のこどもたちと重なって見えた。
──ああ大変だったなと。私たちは生きていくだけの経済力もあって、うちの息子は日本に戻った時は両親が日本語をちゃんとしゃべっていました。それでも、日本の小学校の1年生に入った時は、あんなにいじめられたのに、この難民のこどもたちはいったいどうなるのと。親もない、経済力もないのに。だからセンターで学ぶこの3カ月の間になんとかしてでも、少しでも力を付けてやらなきゃいけないと、なんかそのときハッと思ったわけですね。
教科書があれば、こどもたちが力を付けるのに役立つだろう。屋代氏は根本氏の言葉にそう思い賛同した。
二人三脚
二人はセンターでの業務が完了した後の時間を利用して少しずつ制作を進めた。根本氏は当時を次のように回想する。
〔2015年・東京都文京区〕-1024x574.jpg)
──始めた頃は難民センターの終業式の後にとか。終業式は一緒に集まりますから。普段は曜日が違うので会うことができない。他の人に迷惑もかけたくありませんでしたし、なんとなく何をやっているのか見られないように教室に鍵をかけちゃって。それは覚えています(笑)。
屋代氏は、センターの外でも時間を見つけては打ち合わせをしたという。
──渋谷のフランセなんかでやったの。渋谷の駅の前に、もう今はないと思うけどフランセっていう喫茶店があったのね。その頃はそのもう一人の先生も一緒に入ってやっていたんですけど、そのうち彼女はもうちょっとできないということに。二人になったから、家がたまたま西荻駅を挟んでこっちに10分、こっちに10分で自転車でひゃっと集まって。西荻駅のお店はルパンじゃなくてなんだっけ、地下のね。喫茶店。ルノアールだ、それがあったんですよね。あそこでやったような気がするんだけど、自転車でひょいひょいと乗っていって。先ほどお話ししたセンターで作ったこどものための教案をベースにして、2人で文や絵の案を持ち寄って。たぶん2週間に一遍ぐらい、自転車で西荻駅の所に行って。不思議なことにそれぞれの案に何の抵抗もないというか、なんだか全然お互いにいちゃもんなんかつけた記憶がないんですよ。
二人は二週間に一度のペースで集まり、自分の書いてきた教科書の原稿を見せ合った。屋代氏と根本氏による二人三脚での作業が1年ほど続いた頃、一次原稿が完成した。屋代氏は笑いながら話す。
──なんかもうすらすらと。そのあとのいろんなことは、お互いいちゃもんつけてけんかするんですけど、その時代、なんとまあ二人は素直でもう一心同体というか、なんか一生懸命作ったんですね。
一人の人間の成長物語
『ひろこさんのたのしいにほんご』はタイトルに主人公の名前が用いられている。しかし、実はこのような形態をとる日本語教科書はさほど多くはない。屋代氏はこの形となった理由を次のように述べる。
──私が中学で英語を勉強した頃って 『Jack & Betty』っていう教科書があったんです。中身はすっかり忘れましたけど、それに倣ってタイトルは人間がいいなというふうに思ったわけです。で、男の名前も一緒に入れるのもなんか変だから、女の子の名前だけにしました。
教科書の登場人物は、“ひろこさん”を始めとして、家族や友達、隣人で構成され、物語の進行に即した会話で学ぶことができるようになっている。

ひろこさんという名前には、『おしん』の出演女優田中裕子氏のように生き抜いて欲しいという想いが込められていたことは冒頭で述べたが、ひろこさんのイメージ構築にはもう一つエピソードがあったと根本氏は語る。
──主要な登場人物を女の子にしたのは、自分たちが女だったからかもしれません。「女の子が主人公で、男の子たちの抵抗はなかったんですか」とかいう質問を別のところで受けたことがありますけど、特にそういうことはなかったですね。それから、ひろこさんの三つ編みは私がこどものときにしていた髪型なんです(笑)。外国にルーツを持つこどもではなく日本で生活する日本人のこどもを主人公にしたのは、日本の生活とかそういうのに慣れてもらうということと、私たちはその生活しか知らないので、日本人の女の子を選びました。結果的には難民のこどもたちが自分のことのように思って喜んでくれました。
このひろこさんの家族像や設定については「家族や環境に恵まれた上流階級のようでよくない」といった意見もあった。しかし、屋代氏はそうではないという。
──暖かくて楽しくなくっちゃだめ。大変な境遇にあるこどもたちを相手にするからこそ、夢のある教科書にしなくちゃだめです、夢がないと。︎子供のための教科書は「ちーちーぱっぱ」だとも言われますけど、そうではないんですね。きちんとした内容も夢もないといけないと思っています。
お互いの得意分野を活かした分担
教科書はこどもたちへの思いの詰まった、優しい雰囲気を持つものになった。文型練習は、こどもたちが想像し理解しやすいようにたくさんのイラストが使用されている。それらのイラストは、表紙から本文まで全て根本氏が描いたものだ。

こどもたちに英語を教えていた経験のある根本氏は、絵の大切さに早くから気づいていた。
──媒介可能なことばも少ないので、やっぱり絵を見て、絵で理解してもらうっていうか。絵は上手ではなかったですけど、こどものときから習っていました。自宅の近くの幼稚園に絵の先生が来てやっていた絵画教室で、小学校の三年生ぐらいから高校ぐらいまで通いました。この教科書ができる前に、手書きの教材を使ったりしていまして、そのときも必ず私が描いていましたから、もう絵は私というような感じになっちゃって(笑)。絵カードとかそういった物も描きました。
言語的な指導とイラストの両面から教えることのできる根本氏の存在は大きかったと屋代氏は言う。
── 一番最初は、恥ずかしい話なんですけど「おはようございます」「こんにちは」「こんばんは」とか、書いてくれるわけですよね、彼女が。私、なんでこんなの必要なのかしらなんて思ってね。だって『おはようございます』ってことばでやるんだし、私は実践型の人だからイラストはいるのかなって。でも、よく考えてみたら、センターっていうのは3時半かなんかに終わっちゃうから、「こんばんは」っていうのはあり得ないわけですよね。そこで私は気が付いて。なるほど、現場で、ことばだけで教えられることは非常に限りのあることですよね。
イラストを教科書に掲載することで、ことばと共に状況や場面も想像しやすくなるのだ。一方で、文字と歌は屋代氏の担当であったと根本氏は語る。
──屋代さんの字が本当に綺麗なんですよ。だから、練習帳の字も。「字係」でした。私は「絵係」で(笑)。
屋代氏は笑いながら答える。
──そうそう。絵は描けないけれど、字は書けるだろうということで文型練習帳の手書き文字は私が担当しました。漢字練習帳のお手本などの副教材もですね。
レイアウトについては編集者の尽力もあったと屋代氏は話す。
──教科書はレイアウトが難しいのですけれど、各課のレイアウトみたいのは、今もやってくださっているんですけど、凡人社さんに出入りされている皆川さんっていう印刷屋さんにやっていただきました。彼がすごくセンスがあったのね。原稿を凡人社さんに提出すると印刷会社さんに送ってくれて、そこからゲラが上がってきてね。でも、そのゲラが変だなんて、あんまり直した記憶ないね。上手にね、なんかすごく力があって素晴らしい人なんですよ。ねもっちゃんが時々間違って描いたり、例えば、7把だったのに6把しか描いてなかったとかっていうこと、2巻のほうですね。「絵では1把足りないようです」って、気づいてくれた。
根本氏も編集の大切さについて次のように話す。
──レイアウトってすごく難しいんですよね。絵があって、スペースや文字を詰めたりとか、そういう作業は大変だったみたいですね。それで分かち書きなもんですから、特にそれが大変で。変なところで文章を切れないからレイアウトが大変。日本語教科書特有の難しさっていうのがあったでしょうね。
表紙や本文の色についてもアドバイスがあったと屋代氏はいう。
──「カラーで出したい」ってねもっちゃんが言ったから、私もそうしたいと思ったんだけど、3倍ぐらいの出版費用がかかるのね。それで駄目だから、じゃあ白黒でっていうことになったのよね。そうしたら皆川さんが、「表紙ぐらいカラーでしなきゃ売れませんよ」ってアドバイスしてくださったんですね。それで表紙はカラーにしようっていうことに。色々な面で、みんなのお力ですよね。彼がいなかったら、中のレイアウトもどれだけ苦労したことか。とても見やすく組んでくださったんです。あんまりビシャッと文字やイラストが詰まっちゃったら、なんだかわっとなって嫌じゃないですか。特にこどもたちはね。
ちゅうこ秘話
一巻39課の「わたしは星がほしいです。」は、他の課とは雰囲気が異なり印象的だ。経緯を屋代氏は次のように話す。



──あのちゅうこ、かわいいでしょう。でも苦しい部分もあって。39課は「〜がほしいです」が学習項目ですよね。でも、難民のこどもたちに「何がほしい?」なんて聞くのはかわいそうだと思ったんです。何も持ってないし、少なくとも、多くを手に入れられる状況にはないですよね。そこで、物語風にしたんですね。
物語のアイディアは、屋代氏の自宅での珍事から得たものであった。
──たまたまうち、その頃古い社宅だったもので。隣も古いうちだったんですよ。そのうちを壊したら、なんと、そこに住み着いていたネズミがうちの社宅にみんな来ちゃったんですね。もう築60年だかの社宅だったもので入ってきちゃったんですね。ネズミが「ドッドッドッドドドドド」って、なっちゃったんですよ。えらいこっちゃっていうので、わが家全員が協力するわけですよ。そうしたら主人が、似たような落語があったって言うわけ、ネズミがどうとかっていう。それを教科書にも書いてみたらって言ったの。だからなんか、やっぱり人間って何もないところからは書けないんですよね。そしたら、根本さんがなんかすごいかわいい”“ちゅうこ”の絵を描いてくれて課ができたんです。
西尾珪子専務理事の理解
一年間の開発と試用調査を経て『ひろこさんのたのしいにほんご』は完成した。出版するには出版社を探す必要があるが、その前に一つの気がかりがあったと屋代氏は話す。
〔2015年・東京都文京区〕-1024x571.jpg)
──できたはできたんだけど、一つ心配があって、発光ダイオードじゃないけどセンターで作ったものを出版していいのだろうかと思ったんです。それで西尾珪子専務理事に相談しに行きました。果たしてそういうところで開発したものが許されるのかなとは思ったんですけど、「いいことよ」とかっておっしゃってくださって、ほっとしました。しかも、出版に向けて後押ししてくださったんです。團伊玖磨さんの妹さんで大変な名家の出なんですけどね。輝かしく国際日本語普及協会を設立された方で、立派な方なんです。西尾専務理事が「凡人社さんが一番いいんじゃないか」ということで、そこに紹介されて行きました。
凡人社田中久光社長の言葉
凡人社に赴くと、西尾専務理事の推薦もあり無事に出版が決まった。しかし、採算が取れるかを危ぶむ声は多く、自費出版となった。
根本氏は1986年の出版時にはちょっとした騒動もあったという。
──出版できて原本が届いて万歳って喜んでいるときに、漢字の筆順が違っていることに気が付いて。ショックで電車から飛び降りるとかいってね(笑)。
発行してしまった後に気づいた間違いは、もう直すことができない。そこで凡人社に一冊ずつ訂正のシールを貼ってもらった。
──申し訳なくて。家族総出で貼りに行こうかしらなんて言っていたんですね。すごい純情だったんじゃないですか、教科書の出版は何もかもはじめてのことで。
出版された『ひろこさんのたのしいにほんご』は、センターでも難民のこどもたちへの日本語支援に活用された。とにかく、こどもたちに大変に喜ばれたと根本氏は語る。
──本がきたとき、こどもたちがすごく喜びましたから。自分たちの本だっていうので。とにかくこどもは喜びました。表紙の絵の女の子が同じ年頃なので、自分だと思うらしいんです。男の子も、もうすごく喜んで、それでやっぱりすごく教室が落ち着きましたよね。すると先生だって落ち着くし、うちに持って帰っても、お父さんやお母さんだって学びやすいですよね、絵があるから。これは傘だとか、これはサルだとかぐらい、一緒に勉強していたんじゃないですか。なんか、出した途端にクラス全体、こどもも落ち着いたし先生方も「ああ、これで教えればいいんだな」と思って。
人気はじわじわと広がり、今日までにシリーズ全体で10万部を超える発行部数を数える。それは、奇跡のようだったと根本氏は振り返る。
──本当に奇跡です。そう思ったんです。最初の頃は、練習帳が揃っているのがいいんだとかいう声も聞いたことがありますし、媒介語がないから逆にいいんだっていう声もありました。誰でも使えていいっていうことも聞いたことありますけどね。最初は初版を使ってもらえればいいなと思っていたぐらいなんですけど、まさかこんなに長く、いまだに利用され続けるとは夢にも思っていませんでした。
凡人社の田中久光社長も、この教科書には感じるものがあったという。『ひろこさんのたのしいにほんご』発行から30年が経過した2017年度、田中久光社長は日本語教育学会の功労賞を受賞した。それを記念して、15分間にわたる特別インタビューが学会で行われ、その模様は学会公式Webサイトに掲載された。インタビューの中で、田中久光社長は自身のキャリアと出版活動を振り返り、特に印象に残っているエピソードとして『ひろこさんのたのしいにほんご』を挙げ、次のように語ったのだ。
──こどもの本を女性たちがつくったんですね。先生の経験でつくった教科書が本当に売れるんだっていうことがわかりましたね。生活にペーンっと(ニーズに)合っていたやつであれば売れるんだなと。やぼったいけど日本語教育の本ってそういうもんでいいんだといまだに思ってます。
日本語教育を出版・書店という両側面から牽引してきた田中久光社長は、1973年の創業時までを総括した際に、日本語教科書のあるべき姿として『ひろこさんのたのしいにほんご』を例に挙げ、率直に讃えたのであった。
地球の裏側にまで広がる輪
こどもたちと過ごし、教科書を作った難民センターでの8年間の後、根本氏はインドへ渡った。
──日本語をずっと教えていくのに、やっぱり海外でも教えてみたいなという気もありましたし、その時まで東京YMCAでも教えていたんですね。たまたまなんですけど、ちょうどその時に東京YMCAの日本語科が閉鎖になったんです。それで「ああ、もう戻るところもないから、行くところもないから、行ってもいいかな」と思って。
国際交流基金からの派遣で渡ったインドでは、2年間を過ごした。
その間にも『ひろこさんのたのしいにほんご』は広がっていった。二人の“日本語を学ぶこどもたちに広く使ってもらいたい”という大きくて優しい想いはしっかりとつながり、現在でもこども向けの教科書として使われ続けている。
しかし、出版当初は国内での需要も難民センター以外にはなく、日本語教育機関などへの宣伝も一切しなかったという。世界中へ広まって行ったきっかけは何だったのか。
──はっきりは分からないんですけど、海外に国際交流基金のいろいろな日本語のステーションがありますでしょう。そこに、年少者向けの教科書として需要があったんでしょうか。凡人社が推してくれていたらしいんです。
日系人が多く住むブラジルでも、『ひろこさんのたのしいにほんご』シリーズは絶大な人気を誇る。屋代氏の夫がブラジルで偶然聞いたという話で、二人はまた気付かされたという。
──今、ブラジルでは日系3世4世になっている。そうすると、日本語が母語じゃなくなっているっていうんですね、そうすると、なんか夫の知り合いは、『ひろこさん』がたくさん使われてるっていうんですね。それと、おかしかったのはね、場所は違いますが、どこかで海賊版も出ちゃったんですよね。後で許可したんだけど。なんか海賊版が出たから裁判とか言われて、そのコピーをもらったんです。そしたら、本物の『ひろこさん』では、載せるべき数字が抜けていた箇所があったんですけど、海賊版を見たらそこは補充されていたわけです。大変だっていうわけで、次に増刷するときに直したのね(笑)。むこうのほうが素晴らしい、オリジナルよりきちんとできていた(笑)。
シリーズ化と副教材開発
ブラジルの利用者からはもう一つ重要なコメントが寄せられた。
──主人は「あれは日本人が教えるテキストですね」っていったっていうんですよ、その方が主人に。それで私もまたそこでハッと思って。そういえば、だいたいがセンターで日本人がみんな教えたわけですよね。だからこれはなんか音声教材がないと駄目だって気が付いたわけ。ネイティブ教師でなくとも教えやすいように。あるいは学びやすいように。それで、ねもっちゃんが、音声教材を今作っている。また、出版されたあと、めでたしめでたしだったんですが、彼女はすぐにドリルをちゃんと出しましょうと言ったの(笑)。それで、はいはいっていうわけで作ることになったんだけど、文字はこどもがまねして書くから印刷の活字体では駄目だって彼女が言うんですね。手書き書いてっていうから、はいはいというわけで、私が文字は、最初は真面目に下敷きを敷いて書いたんですよ。まだその当時は若かったから(笑)。それで彼女が絵を全部描いて、それも全くいちゃもんなしで。彼女はドリルの文型のほうは、私がやりますと言って文を作ってくれて、それで文字のほうはなんか私の担当で、点々とかなんとかやって書いて、文字と文型のドリルを出して。
他にもシリーズでは、新たな仲間・遠藤宏子氏、永田行子氏を得て、絵カードのPDFが収められたCD-ROMや、『ひろこさんのたのしいにほんご2』、『ひろこさんのたのしいにほんご1教師用指導書』、『ひろこさんのたのしいにほんご2教師用指導書』が制作され市販された。
こどもを対象にした教科書というのは、日本の小学校の教科書を使えば良いという話では決してない。母語としての積み重ね、その国の人間としての生活経験のないこどもには、例え同じこどもであっても日本語教育をベースとした新しい教科書が必要だったのである。

難民のこどもたちへ向けた教科書開発の裏には、屋代氏が息子たちの苦労を見てきた経験が大きく関わっていた。息子たちの苦労を見てきたからこそ、目の前のこどもたちが学ぶ難しさが理解できたのだ。教科書の細かい作業は、その息子たちも手伝ったという。
──「ねもっちゃんが『やりましょう』って言ってくれなかったら、こんな本は生まれてなかったろうと思うんですね。それでその時、自分の経験がよみがえったから。だって自分たちはすごい恵まれているわけじゃないですか、長男だってなんだって。それでもこんなに苦労させた。むこうに行って苦労して、やれ帰ってきたらまたすごい苦労、日本人であるのにすごい苦労させちゃったわけですよね。だからこの子たちってもう完全にお客さん扱いされてしまっているなと思って。お客さんっていうふうに言いますでしょう。まあ置いておいてくれるでしょうけど、それじゃかわいそうじゃないですか。自分の人生を生きられないですよ。だから『ああそうか、力になるんなら』と思って教科書を作ることになったんです。ずいぶん息子たちも手伝ってくれましたよ。点々とか教科書に書いてありますでしょう、「あ」なら「あ」をなぞるための点々。あれ長男がやってくれたの。」
経験と実感に裏打ちされた屋代氏の熱意が、何も分からず日本へやってきたたくさんのこどもたちの、その先の未来を創る助けになったのである。
こどもをみつめる優しさからうまれた教科書
1986年10月に刊行された『ひろこさんのたのしいにほんご』の冒頭には屋代氏と根本氏が次の言葉を記している。
──本書の主人公、ひろこさんは、日本に住む9歳の日本人の女の子です。この本で学習することによって、日本語を楽しくわかりやすく習得させるだけでなく、ひろこさんの生活や、その家族や友人とのかかわりあいを通じて、日本の生活や習慣も、自然に学べるように心がけました。本書が、児童向けの日本語教材として、少しでも学習者の助けとなるよう願っています。
初版から30年経った今でも、現場のニーズに寄り添おうとWebサイトでの副教材配信活動は継続している。シリーズ3作目を作ってくれという依頼もあったというが、それは辞退したと屋代氏はいう。
──私もいろいろ考えたんですけど、もう書けないと思ったんですね(笑)。第一、もう長いこと教えていないわけですよ。もう辞めてから20年近くたっちゃって。だからちょっと体験も薄れちゃって、これは書いても机上のなんか。孫たちを取材すれば何とか書けるかなと思ったんですけど、3人とも中学生になって、もうみんな羽が生えちゃって、おばあちゃんの所なんてそんなに、とんでもない用事がない限りは来ないということになりまして、ますますこれは書けないなと思って。それでもう、やっぱりそれは諦めました。それで、今は音声教材をね、ねもっちゃんとインターネットで公開しています。
〔2015年・東京都文京区-〕-1-1024x768.jpg)
自分たちの体験と、現場のニーズを元にして、教材を作ってきた。二人が大切にしてきたのはあくまで等身大の教育者としての目線であり、二人三脚で歩んできたのである。インタビューの最後に屋代氏と根本氏はお互いの関係についてこう語った。
──そういう人と巡り会えたっていうことですね。
可愛らしい絵と、難民のこどもたちの心に寄り添った本文の根底には、屋代氏と根本氏、二人の女性の息の合ったこどもへの優しさがあった。