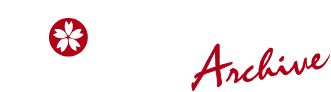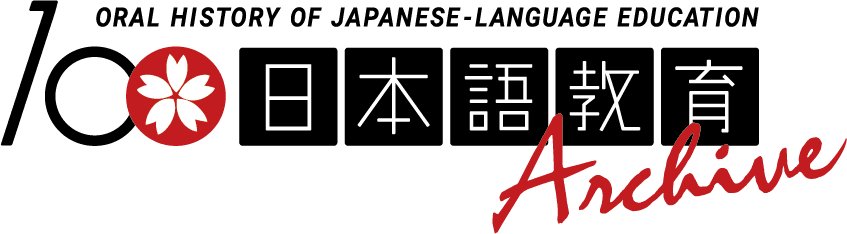03
HISAMITSU TANAKA
新たな日本語教育出版社の設立
田中久光 Hisamitsu Tanaka
1938年兵庫県加古川市生まれ。1961年3月中央大学商学部卒。1961年4月通商産業省入省。1963年に通商産業調査会に出向し出版物編集業務に従事する中で日本語教育と出会う。1973年に江戸川区小島町にて凡人社を創業、代表取締役社長に就任。日本語教育関連書籍を扱う書店業と出版業の両輪という新しい事業形態を切り拓き、戦後日本語教育の発展を国内外への日本語教材の普及や開発、人材育成、学会や研究活動の振興など、あらゆる側面から支えた。2003年にはNPO法人日本語教育研究所を立ち上げ、理事を務める。長年にわたる多大な功績を讃えられ2017年度文化庁長官表彰、および、2017年度日本語教育学会功労賞を受賞。2018年には文化庁創立50周年記念表彰を受けた。
-

株式会社凡人社
1973年に江戸川区小島町にて創業。社名は、常に凡夫であることを基本理念とし外国人にとって発音が容易であることも考慮して名づけられた。1978年に麹町店を千代田区麹町に開設し、倉庫流通業務を行う注文センターを港区港南に設置。1988年に大阪市淀川区に大阪店開設。1989年国際交流基金日本語国際センタ-内に売店を開設。1990年関西地区物流拠点として加古川倉庫を開設。1997年国際交流基金関西国際センタ-内に売店を開設。現在では、本社(東京都千代田区平河町)、麹町店(東京都千代田区平河町)、大阪事務所(大阪府大阪市中央区久太郎町)、流通センター(新潟県新潟市西蒲区)を有し、出版部門、IT関連部門、研修部門、販売部門で組織されている。日本語教育用図書や日本語学習用図書、日本語教育関連学術書を刊行し、また、日本語教育関連図書の販売と国内外の流通も担い、日本語教育全体の発展を牽引している。
都会育ちのガキ大将
1938年12月、田中氏は兵庫県加古川市の歯科医を営む家系に長男として生まれた。“久光”という名前は祖父が尊敬していた島津藩主からとったという。幼稚園は神戸の私立女子高の付属に通い、7歳の時に戦火を逃れ疎開した。都会のお坊ちゃんが突然経験した田舎暮らしは、世界が違って見えたという。
── 都会からきたから、最初はいじめられましたよ。毎日、ケンカして、みんな、川にぶち込んでやった。それで俺はいつも有名だった。「あの野郎はひどい」って。
都会からやってきたわんぱくなガキ大将に、周囲は驚いたという。農地や家畜の多い環境に救われ、食料の面では苦労したことはなかったが、戦時であることを肌で感じることもあった。
── 田舎で比較的楽だったのかもわからないけど、空襲で神戸がやられる、明石がやられるというのは見えました。空が真っ赤になってね。「どうなっちゃうんだ」って思うぐらい、パカパカパカパカってやってるわけだから見えるわけですよ。お爺ちゃんに山の上へ連れていかれてね「お前ら、よく見てろ」って言われて、「戦争したらこうなるんだよ」ってね。「これはすげえことになると思う」ということしかよく分からなかったけどね、その時分は。

終戦を迎え、小学校へ上がった田中氏は、5年生の時に父親を結核で失った。
── だからほとんど、俺ら兄弟はお袋に育ててもらったようなもので。お袋の実家が、バックボーンになってくれたわけだな。それが、医者だったり、歯医者だったもんだから勉強もしたし、「お前、遊んでばっかりいるんじゃねえよ、高校へ行かなきゃ」ってよく言われて。内心、「なんで行かなきゃいけねえんだよ」って思ってたわけ、昔は。中学校から4人か5人しか入れない、なかなか入れない所だからね。でも、なんだか、その中に入ったんだよ、不思議に。
1954年に地元の名門校である県立加古川東高校へ進学。数学は苦手だったが、作文や国語は得意。中学、高校では弁論大会によく出場した。スピーチが得意で弁の立つ生徒だったが、わんぱくぶりは健在だった。
── いや、もう先生に怒られたのは俺が一番だったそうです。有名です。校長室で立たされたのも俺が一番多いんだって。それで最後に「お前、卒業できるとは思わなかった」って言われたんですから。
進学と母の言葉
高校生活を過ごすうち、次第に進路を意識し始める。親戚筋には歯科医が多かったものの、田中氏本人は医者には向いていないと言われていた。
── 「お前は商売に向いているよ。まともなことをやらないで、商売やってろ」と、家族みんなに言われてた。
大学に進学して英語の勉強をしたいと考えるようになった。
── 一応ね、中央に行くのも決めたわけじゃなかったの。俺は、青学へ行きたかった、女の子に美人が多いとかね。そこへ行って、英語の勉強をしたいと思っていたんだよ。有名な先生がいるし、これは面白そうって。
志望は青山学院だったが、母親からは中央大学を勧められた。
── 中央っていうのはお袋に決められちゃって。「学費が安いんだからこっちでいい」って言われて。それでそのときに、「公務員になりなさい」って言われたわけだよ。親が言うわけだから一応、しょうがねえなって、中央に入った。それで、公務員になるためにやることはずっと一応、やっていたわけ。
公務員試験の準備をしつつ、商学部で4年間を過ごした。大学時代はたくさんのアルバイトを経験した。
── アルバイトはいろんなこと、全部やりましたよ。NHKだとかね。お金集めですよ。うまかったよ、俺は。

弁論大会で培った話術と、持って生まれた統率力の強さはこの頃から開花していた。
卒業論文では何を研究したか覚えていないというが、提出した時のことはよく覚えている。
── 先生のうちに、お酒と一緒に論文持っていって奥さんに渡したような気がするんだよ。それはもう、後でずっと奥さんに言われたけどね。「あんたぐらいよ、あのぐらい堂々として持ってきたのは」って。
卒業を目前にし、田中氏は進路を決めかねていた。
── 公務員試験を受ける段取りはずっとやってたわけ。それで最後にゼミの先生から「お前行くとこないよ。役所でも行け」って言われたんだよね。「どこか分からないけど、とりあえずあんた役所行きなさい」と。で、受けて、そしたら、あれよあれよと。
試験に合格し、通商産業省に入省することになった。
通産省から出版界へ
通産省に入省後、しばらくは輸入業を営む会社からの申請受付を担当した。商社が海外から物品を輸入する際の手続きを受け持つ割り当て業務である。役所勤めで苦労したのは、厳しい年功序列だったという。
── 先輩の顔を立てるってこと。大学の先生もそうなんだけど、一番難しいのはそのへんなんだよ。だから出来ないなら出来ないで「あいつはもう、どっちみち馬鹿だからいいんだよ」って言われるようになったほうが得なわけ。いじめられなくて済むわけだ。目立っちゃ駄目なわけだ。それを、俺はなんでもかんでもすぐ目立つから。それで苦労したの。
また、田中氏が所属していた頃の通産省は、日本の高度経済成長の一翼を担う省であった。仕事も桁違いに忙しく、また、うまく立ち回らなければ会社側から因縁をつけられることも多かった。
── ぐーっと伸びてるところだったから、それだけにいつも外から厳しく見られるわけですよ。食事も企業の連中がいくらでもおごってくれるわけだけど、俺は「はて、今の誰だったっけな」ってすぐ忘れちゃうわけ。それで、その会社の意にそぐわない対応をすると「なんだ、お前のとこのあの役人は」って上司に言うわけです。年がら年中、文句言われて、課長に呼び出されて「お前、何か言ったか?」って、「別に何も言いませんよ」って。「お前気をつけろよ」って言われた。
幼少期から変わらない豪胆な性格は枠組みには収まりきらなかった。しばらくすると通産省から通商産業調査会への出向が決まった。これをきっかけに、田中氏は初めて通産省を出て、外務省や厚生省、文化庁の前身など様々な省庁について知ることになった。
── 記事をつくって出版する仕事です。外務省や厚生省なんかから原稿を取ってきて、要するに役所の役人に記事を書いてもらう仕事ですね。大学の先生に頼むのと同じ。それで出版物を出して、それを全部商社に売っていくわけですよ。
二年間通産省で働いた経験に加えて、この調査会での仕事を通して、役所と共に仕事をする際の要領を学んだ。また、出版という分野に携わったことで、後に活かせる人脈づくりにも役立った。
実は、日本語教育との縁が生じたのもこの頃である。
── 外国人に日本語を教えることを考える会があったんだよ。それが文部省かなんかについてたわけ。それを聞きに行ったことがあるんですよ。そしたら、「お前、興味あるのか。お金にならないからよしなよ」って言われたんだけど。
当時、日本語教育界では名の通った文部官僚にそう言われたことを、田中氏は今でも覚えている。日本語教育と国語教育とは別物だという考えを主張しているグループの中の一人だったという。
── その人たちは、誰も役所で偉くならない人だったんですよ。でも、そういう人の話を聴いて、影響されちゃったんだね。俺が覚えちゃったんだよ、日本語教育のことを。その人が立派なことを言ってるからね。それで、俺が間違った。日本語教育に進んじゃった。
こうして田中氏は日本語教育にぐんぐんと引き寄せられていき、1973年に満を持して凡人社を創業することとなったのである。
妻の後押し
凡人社と日本語教育との関係は、切っても切れない。そもそも出版社を立ち上げようと考えたきっかけは、1972年の国際交流基金の発足にあったという。
国際交流基金が発足し、本格的に日本語教育の振興に資金が投入されるようになった。しかし、国際交流基金がプログラムを進める際につくる刊行物や広報物を発行し、国内外に発送するための機関が無かった。
── ちょうど調査会で、記事を一生懸命に書いているときに外務省がいつもそれを言っていたわけ。「無いから困るんだよ、田中」って言って。こういう性格だからさ、「どうだ、お前やればいいだろう」って言われたら、乗っかるんだよ、俺は。
しばらくは倉庫を持ち、国際交流基金関連の刊行物の保管や郵送の下請け業務をしていたが、今度は日本語教育関係者から、自分たちの本もやってくれないかという要望が届いた。それらを一手に担うために、ついに出版社を立ち上げることに決めた。
── やらなきゃいけなくなっちゃったわけ。「この本をお前のとこで売ってくれや」、文化庁の本だとか、早稲田の本だとか、ああいうのを全部俺のとこで売れるようにしたわけです。「田中のとこで売れや」って、みんなに言われてた。
しかし、いざ会社を立ち上げてみると、初めてのことばかりで苦労の連続だった。
── 経理はできねえし、何もできなかったんだからね。よく起業できたと思うよ。嫁さんに苦労かけましたね。ほとんど銀行は、嫁さんがやってくれてましたから。「あなた、計算もできなくてよく会社できるわね」って言われてたんだ。俺は、物は売り買いするけど経理は全然分かってない。
妻の支えは力強かった。会社を興すと相談した際も背中を押してくれたという。
── 凡人社の外国人の面倒なんか見たのは、嫁さんのほうが面倒を見てますよ。それが、たまたまうまく(分業として)合ってたんだよね。外国人の面倒を、全部やってくれました。
立ち上げ直後は国際交流基金に関わる仕事を多くこなした。
── 国際交流基金から海外に本を送ってるわけ。大学の先生が作っている本だとか、いろんな教材だとかあるわけ。それの送りを全部、うちがやっていた。いろんなことをやらなきゃ食えないんだから。それだけじゃ食べられないですからね、結局。だから国際交流基金で郵便局やってたよ。
また、出版や郵送に全く関わりのない業務も喜んでこなした。
── だって、基金の偉い人の部屋の石まで洗ってたんだから、凡人社が。知らないでしょ。枯山水みたいなのがあって、その石を洗いに行くっていう。なんでもやってたんですよ。
世界の日本語教育に貢献する
しかし、一方で、それらの仕事を通して直接的な人脈をたくさん得ることができた。それはその後の会社の発展に大きく役立った。凡人社の社是である「世界の日本語教育に貢献する」も、国際交流基金関係者とのやりとりから生まれたのだという。
── 基金に出向していた鳥山さんっていう役人がいたんです。大蔵省の役人なんです。それがね、世界、世界ってことを年がら年中言ってたわけ。日本語教育の先生は、世界っていう言葉を使わない。それを鳥山さんは使っていて「あ、これはいいね」と思ったの。だから、会社が小さい割には世界という言葉がついているわけですよ、俺のところの名前はね。それを結構大事にしていて、基金の物を送るときに世界中に同じ「世界の日本語教育に貢献するにほんごの凡人社」とフレーズがついているわけです。
ロゴマークにも大切な意味が込められている。
── あれはね、カイロの女王の首飾りにあるマークなんですよ。それを、おもしろいと思って使ったの。こんなに世の中に出ることになるとは思わなかったんだけど。最初、つくったとき、取引相手がマークマークって言うわけよ、お客さんが。基金で日本語の勉強をする人たちがうちで本を買うわけです。そのときも、このマークを教科書につけろって言うの。だったらってことで正式なロゴマークにしたの。
ホルス神がモチーフとされたロゴマークには、羽ばたくという想いが込められた。

社是とロゴマークは凡人社発行の全ての本に、そして、凡人社が扱う書籍の梱包箱の全てに印され、世界中の大学や機関へと送られていった。マーク一つで凡人社の存在が、使う側にも売った側にも感じられる。小さくとも確かな力として、世界中の本棚に刻まれているのである。
未来を支えるために
凡人社は、出版社として出版物を刊行すると同時に書店を展開するという点で、他の出版社とは一線を画している。この体制を定着させることは容易ではなかった。
── 結局、作ること、売ること、両方できるということ。それを周囲に認めさせた。それを出版社にも認めさせた。それから本屋にも認めさせた。それは、やっぱり40年間やった結果。初めはもう絶対認めてくれなかった。「駄目だ」と言われるわけよ。相手は東販だとか日販、でかいから。それで、年がら年中けんかしてましたから。「おまえんとこは飯はまずいから食うのやだ」っつって、あっちのでかいとこの社長とやるわけですから、けんか。有名だったんです。
けんかばかりのガキ大将は社長になっても健在だった。達者な弁論を、会社と自分の信念を守るために駆使した。
── 「お客がやってんだからいいじゃねえか」って。それはガンガンやりましたよ。
とにかく日本語教育という分野を、ひとつにまとめるようなシステムが必要だと感じていた。それは、役所という縦割り社会に身を置いたことのある田中氏ならではの視点だったのかもしれない。
── 俺の仕事として日本語教育がくりっとまとまったことだけは認めてよ。出版社から何から全部俺まとめたんだから。ぎゃって言ったらみんな言うこと聞きますからね、結局。
会社の骨組を整えた後は、他社との連携も柔軟に行った。
── つながってったほうが特だよって、俺は常に説得してるわけです。何かあったら俺に言ってこいと、俺が話をつけると。年がら年中やってますよ。今でも新しいココ出版って会社の全然儲からない株を買わされたりしてますもん。でも、そういう発想というか思想が、みんな集めて、そして「みんなでやっていくんだ」っていうふうに思った。
初めは売れなかった本が売れるように道筋を整え、流通を動かせるようになると、仲間内で凡人社の名前は有名になった。
── だんだんと、いろんなことをやらされちゃうわけよ。「あいつにやらしとこう」って、みんなが言うわけです。早稲田の木村宗男教授だってそう。いつも「田中のとこでやらせろ」って言ってくれた。
教師を育てる
どんどんと繋がっていく人脈は、たくさんの新しいチャンスを運んでくる。凡人社は出版業と書店業との二本柱で経営される。珍しい業態だが、それ以外にも、教師の研修や学会の後援など、多角的な事業を行っている。その根底にあるのは、常に長い目で見た日本語教育界の未来のために、という考えである。
── お客さんから言われることが一番多いんですけど。僕らの日本語教育の世界で、何が足りないというのは、先生が足りないんだよ。先生の勉強する場所が、今までは国研(国立国語研究所)にあったんですよ、基金(国際交流基金)にあったんですよ。それが全部なくなっちゃった。だから学会がやらなきゃいけないんだけど、全部はどだい無理なわけだよ。今一番、俺らが心配しなきゃいけないのは、未来の先生を育てるってこと。
日本語教育の中心で活躍している人々のサポートとして、出版業を越えて出来ることがある。そのために、凡人社は学習者向け教材に留まらず、教師向け書籍の刊行にも取り組んだ。また、教師そのものにきちんと価値が見出されるように協力もしているという。
── 業界で考えなきゃいけないのは、その先生を偉くしなきゃいけないってこと。ということは、名前を売らなきゃいかんわけ。アルクがやるとか、俺のとこがやるとか。それで三カ所の出版社で、一つの先生の本を出せばその人が偉くなるわけだ。
そこで育てられた教師は、優れた実践に加え優れた人材育成をする。総じて、日本語教育界が発展していく、というシステムが大切だと田中氏は語る。

すでに40年を超える歴史を持つ凡人社だが、創業当初苦労したのは、目をかけた研究者や教師が、日本語教育を離れてしまうことだったという。
── 結局、移っちゃうんだよ日本語教育から。国語の中にいっちゃったりね。やっぱりお金だよ。食っていけなかった。だからみんな二つ足をかけてるわけ。それでどっちのほうがええかなっていって。
そして今までで一番悲しかったのは、3.11の時期だったという。
── 要するにこないだみたいに海外の子どもたちが全部いなくなっちゃった、だーっと。いなくなって、それは苦しかったですよ。
留学生が一度にいなくなってしまった状況に、日本語教育界全体としてもっと危機感を持つべきだったと振り返る。一方で、その反動のように日本語学校が増えているのが現状である。今後の伸びが期待される日本語教育界で、それでも何にも優先すべきは教師の育成であると田中氏は述べる。
凡人の力
凡人社は、その社名が印象的である。
── 凡人だから凡人でいきなさいって意味、その一言。
「凡人」とその会社がつないだ人脈が、凡人社と日本語教育とを深く結びつけていった。
── ずいぶん面倒を見てもらいました。日本語教育にだんだん引っ張り込まれたのは、先生の中の仲間意識というのがあるんですよ。「ああいうのを仲間に入れておかないと、俺らの世界は大きくならないよ」って、常に先生方の頭の中にあったんじゃないかな。
少しでも可能性を感じれば、その人や会社を育てようとする。その意識があったからこそ、今の日本語教育があると田中氏は考える。そして全員で伸ばしていこうという気持ちが今、足りていないと感じると言う。
── あの人はこういうところで、うんと伸びるんじゃないのとか、向いてるんじゃないのとか。あの子は絶対に入れておけよ。常にあったわけですよ。先生方が集まっていても「あれは仕事できるよ」。俺なんかもそうなんだけど、常にあいつできそうだなと思うと、名前を教えてもらいたいって常に言われた。それで、真ん中に置いとかなきゃ駄目だと。どこだ、筑波か、おいたらこうしろと。どこだ、東か、あれは、全部教えるわけ。いいのがいるよって言ったら「それ、誰や、名前言え」って、呼ぶの。それで授業をやらせる。そういうことが周囲の人がやってくれたから、みんな伸びていった。今、それがないんだよ。
可能性を脅威として潰してしまうのではなく、共通の未来のために育成する。日本語教育界において、その風潮が弱まってきていることを危惧しているという。
教師を育てるための活動として、凡人社は日本語教育関係の学会の立ち上げにも奔走した。凡人社がスポンサーになり、台湾にも2つの日本語教育関係の学会を作った。
── 誰もやりたがらないから凡人社がやってきた。そういう話はみんなよく知っているよ。はじめは「なんだ、凡人社がみんな金を集めているのかよ」って言われてた。でも、いいじゃないの、学会作るのに、金は必要だよ。出してくれる人がいればいいじゃないかって、俺に出そうと誰に出そうと同じなんじゃないかと思ってました。初めはそれでもう誤解をされるわけ。あいつ何を狙っているんだと。別に狙っているわけでもなんでもない。好きでやってるんだからしょうがないだろってことだよね、結局。それで、少しずつ理解もされるようになって、いろいろな学会も盛り上がっていった。
そうした活動を通して得た経験や知識を、いつしか若手に伝えて欲しいと言われる立場になっていた。
── 話をして欲しいって言われたりもするようになった。筑波の何年か卒業会を全部俺、出ましたよ。「日本語教育はお金にはなんないよ、お前ら」って話をしたんですよ。みんなの前で言うもんだから、先生方びっくりしちゃうわけだけど、偉くならなきゃ駄目だって言った。それで、勉強しろよと。大学院へ行かなきゃ駄目だと。
若手たちの活躍の場を広げるために、凡人社は日本語教育界のバックアップをし続けてきた。
学会のみならず、海外から帰国してきた教師たちの居場所としてNPO法人日本語教育研究所(理事長:西原鈴子氏)も立ち上げた。すぐに利益に結びつく業界ではないからこそ、教師たちにはきちんとした居場所を確保しておく必要がある。現場の中にいる教師たちからは見えにくい、全体を俯瞰した上で補完されるべきものを、出版社という立場から支え続けてきたのだ。
世界の本棚へ世界の学習者のもとへ
日本語教育に関わり続けた半生を振り返り、田中氏は今、こう語る。
── 日本語教育からは世界観ってのを初めて教わったなと思いますね。要するに、やっぱり日本人はちょっと世界に対する意識が狭過ぎるよねと。やっぱり外国人っていうのは、外国人に対して理解があるよね。世界中回るのと同じようにして、勉強させてもらったなとつくづく思ってますよね。だけど、これだけ、何ていうのかな、いろんな話ができるのは幸せだったね。
長期にわたる日本語教育への貢献が高く評価され、田中氏は平成27年に文化庁長官表彰を日本語教育界で初の企業人として授与された。
── 良かったねってみんなが言ってくれたから、「おまえ結構人気あんだな」ってみんなに言われたんだから。「いや、俺は文句ばっかり言ってるわけじゃねえぞ」っつって。何より周囲がびっくりしてましたよ。「なんだ、おまえもらったか」って言うんだよ、役人たちも。
笑って振り返るが、今後はもっと様々な職種の人に対する評価や表彰を増やしていくべきだと感じているという。日本語教育を推進するのは、決して研究者や教師だけではないからだ。
そして、今後の日本語教育において、いわゆる日本国籍のネイティブ以外も教師としてしっかり認められるようにすることが大切だ、と田中氏は考える。
── 現地の人が、外国の人がやれるようになれば日本語教育が倍になる。減るんじゃなくて増えます、飛躍的に。日本語ってみんな世界中にやりたい人ばっかりなんですよ。それでプラスになるわけですから。それを考えなきゃ駄目でしょうね、結局。
口が上手でけんか好き。人を育て束ねた田中氏は、その才覚と熱意で日本語教育界をがっしりと支えてきた。「凡人」という名を冠する田中氏が築いた会社は、結んできた人脈と、それを世界へ還元していくことの意味をよく知っている。
日本語教育界全体を、そしてその進む先を常に意識し、出来ることを怠らない。その理念は世界の本棚へ、そして学習者のもとへ着実に届いている。