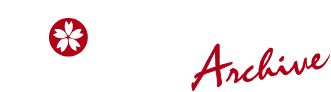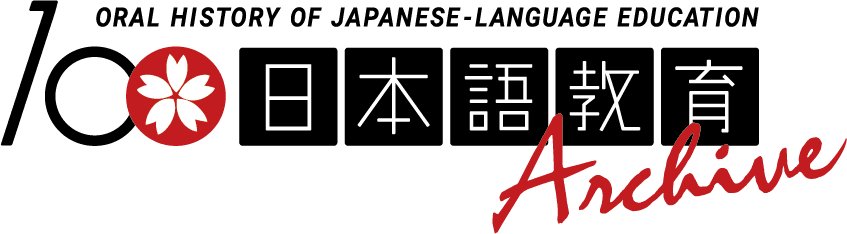05
TAZUKO UYENO
一本の道をゆく
上野田鶴子 Tazuko Uyeno
1935年愛知県名古屋市生まれ。国際基督教大学教養学部卒業。国際基督教大学大学院教育研究科修了。フルブライト奨学生としてミシガン大学留学(修士:言語学)。ミシガン大学博士課程言語学専攻修了(博士:言語学)。国際基督教大学語学科助手、東京大学医学部音声言語医学研究施設専任研究助手、同専任講師、国立国語研究所日本語教育センター第二研究室長、同普及部長、東京女子大学現代文化学部教授、放送大学客員教授を歴任し、日本語教育環境の整備と、日本語教育従事者のネットワーク構築、人材育成に尽力した。また、この間、文部省学術審議会専門委員、国語審議会委員、国際交流基金運営審議会委員、日本語教育振興協会審査委員会委員、国際文化フォーラム評議員、言語文化研究所評議員、国際日本語教育普及協会評議員、日本語教育学会監事、外務省外部評価委員会委員、特定非営利活動法人日本語教育研究所理事長など要職を務めた。2005年、瑞宝双光章を受章。2013年、国際基督教大学DAY Award受賞。2021年度日本語教育学会功労賞受賞。
教養に満ちた家族に囲まれて
上野氏の言語感覚の素地となったのは、幼少期に接した数々の方言である。そして内面を形作るのは、祖母の生き方だ。この二つの大きな要素は、戦時中の多感な幼少期と、切っても切れない関係にある。
名古屋、西宮、岩手という三カ所で小学校時代を過ごした上野氏は、それぞれの地域でそれぞれの言葉に親しんだ。家庭内では標準語を話す家庭であったために、家の中と外での言葉の違いは、当たり前かつ不思議な感覚だったという。
〔1938年・愛知県名古屋市〕-1-1024x576.jpg)
──最初は戸惑いますよね。場面とその使用を見ながら、意味の違いを無意識に分析するというような習得の仕方をしています。最初の自分が持っていた、話している言葉。これも国語とか日本語っていう概念ではなくて、私の言葉なんですけど。それと周りの人が話している東北弁というかずーずー弁というのか、が違うなという意識で。
自らが発する言葉とその土地ごとの言葉との違いを肌で感じ、その地で過ごすことで身につける。その経験は、言葉の背景に気づくきっかけともなったという。
──方言に接して、ある程度それを習得していると、やっぱり言葉が使われた文化っていうのかな。その背景にある文化も見えてくるなっていうのが、大きくなってもそれは感じたことなんです。
小学三年生の時に、岩手県の祖父母の元へ学童疎開することになった。疎開は二年半続き、その間の体験は上野氏にとって大きな意味を持つことになる。
──両親がいない2年半っていうのは、まさに自立でしたね。
祖父は慶應義塾大学で福沢諭吉から教育を受け、祖母は東京女子高等師範学校出身という、向学心のある祖父母だ。
──別に特に、特別な教育をしてくれたわけじゃないんですけど、祖父母の家の雰囲気が、非常に好奇心にも恵まれるような、好奇心を満たしてくれるようなね、非常に自由にさせてくれたんですね。
祖母は当時珍しく、結婚をしてからも女学校の教師を続けていたという。自分の身につけたもので社会に貢献するのだと、終戦後には自宅で、農閑期の農村の子女へ向けた中等教育の場として私塾を開いた。このような祖父母の下で、両親からの愛情の代わりに大きな影響を受けたと、上野氏は振り返る。それは特に、人としての生き方に通じるものだ。
──誰にでも本当に同じ態度で接していた祖母の毎日の姿が、私は今になってみると、なんていうのかな、印象的だったんじゃないかと思うんですね。
終戦後、農地改革が起こり、徐々に田舎の状況が変化していく過程も、間近に見た。特に祖父が地主であったために、その改革は身近だった。
──現実を十分に見たわけじゃないんですけど、でも不在地主が地主の地位を失って、そしてそれまで小作をしてくれた小作人たちに、土地が分譲されるっていう時代を見たわけですね。終戦を境にして祖父母のそれまでの生活とそれ以後の生活が変わるっていう、その端境期も垣間見てるんですね。
その転換期にあっても、祖母の態度は誰に対しても公平だった。終戦後も食料難のため、五年生まで岩手で過ごした上野氏は、祖母の生き方に強い印象を受けた。
親元へ戻り、神戸女学院中等部へ進学した上野氏は、「自分のことは自分で」という教育を母親から教え込まれたという。
──母も教育を受けていて。でも、当時の銀行員の妻っていうのはやっぱり主婦で、転勤について行ってっていう感じですよね。だから母はしたくてもできなかったのが、自分の本当に持っていた才能を生かすことだったと思うんです。でもその代わり、家事とお裁縫、洋裁は習いに行かないでうちでしなさいって言われたんですよ、私は。だからお料理と洋裁ですよね、洋服を、まあ自分の洋服は自分で縫いなさいと。それで家事も、私はいつも手伝わされてました。
自分のことは自分でできるようにならなければいけない。料理、洋裁に始まり、煙突掃除にアイロンの修理、何でもやった。そして、女性は仕事をした方が良いというのも、母親の言葉だったという。
〔1950年・兵庫県西宮市〕-687x1024.jpg)
──仕事ができるっていうことは大事なことだって。そういう意味ではもしかしたら、母の考え方は当時としては進歩的だったのかもしれない。
恩師との出会いと祖母の言葉
教育を受けた家族の中で育てられた上野氏にとって、大学へ進学し学ぶということは極めて身近なことであった。
1954年、日本の英語高等教育を牽引した国際基督教大学(以下、ICU)に二期生として入学する。入学後にアドバイザーとして出会ったのが、上野氏が恩師と語る小出詞子教授だ。
小出教授はオーストラリアで日本語教育の実績をあげた父を持ち、日本語教育主任として日本語教授法の授業を担当していた。大学で日本語教育と出会い、勉強を重ねるうちに、上野氏は英語教育と日本語教育の見られ方の違いに気づく。
──日本語教育っていうのが、英語教育とは全然違った見方をされていた時代です。というのは、私はたくさんの先生に英語教育を受けているわけです、ICUで。ICUに入ったらもう英語教育がトップなわけですよね。それを受けないでほかの道に走るのは、これはおかしいと思われる時代なんですよ。私が日本語教育をしたいっていうことを、英語教育をなさってる先生に言ったら、「そんな道なき道を行くんですか」って言われたの。「ICUに来たのになぜ?」って。でも、その先生にとっては英語教育がもう全ての上に君臨してるわけですよ、当時はね。それなのに、道もないような、誰もしてないような日本語教育の道に将来を探すのかっていうことで、何人もに反対されました。先生方にですよ。
風当たりのきつかった日本語教育に携わりたいという上野氏の背中を押したのは、小出教授だった。「次は留学ね、フルブライト受けたら?」と、当時大学院修了間近だった上野氏に小出教授は提案した。
しかし、家族は留学に反対だった。
──だって、自分たちも外国に行けない時代だから。それと私は第一子で長女だし、大学院を終えてるんだから、次はお嫁さんになるのが当然だというふうに、両親は考えるわけですよね。
けれど、祖母は一人、反対するでもなく「男なんぞに負けるな」と言ったという。
──私、それを聞いて、祖母がもうずっと抱いてたものを今、口から出したんじゃないかと思ったんですね。当時は普通の大学は行けなかったんだそうです。そういうのが、祖母はすごく悔しかったんだと思うの。やっぱり男女の差別っていうことにかなりいろいろ思いがあったんじゃないかと思うんですね。それこそ東北方言丸出しで、それを吐き出したわけですよ。「男なんぞに負げるな」って。本当にね、心に染みましたね。
その言葉を受けて、上野氏は奨学金に応募、合格した。海外に行くことは夢のまた夢だったと笑う上野氏だが、その生き方の根本には、しっかりと祖母の思想が根付いている。
素地を培ったシニアフェロー時代
上野氏はICUではじめて日本語教育に接した。当時から留学生が多く在籍していたICUでの『INTENSIVE JAPANESE』は、他に例を見ない充実した講座だったという。戦時中のアメリカ軍における日本語人材養成に用いられたアーミーメソッドをベースとしたもので、留学生たちは一年間で新聞が読めるまでに日本語を鍛え込まれた。そうした日本語を習得していく留学生の姿が上野氏の身近に常にあった。上野氏は入学してからの三年間、キャンパス内での寮生活を共にした留学生たちの姿勢を見ながら、授業で日本語教育の方法を学んだ。
「私の画期的な日本語教育の訓練」と上野氏が述懐するのは、四年生にシニアフェローになったことである。シニアフェローとは、奨学金を受給し、かつ、授業料が免除される代わりに、教授活動を行うという制度である。上野氏は小出教授の指導の下、今田滋子氏(後の広島大学教授)と共に、初級日本語を学ぶ科目『Elementary Japanese』を受け持つことになった。
読む、書く、聞く、話す、四技能を育成する指導に取り組んだ。このシニアフェローとしての実践活動は、極めて貴重な経験になったという。
と〔1957年・東京都三鷹市〕-1024x671.jpg)
──初めて自分の母語を教えるときの問題点っていうのが見えてくるわけですよね。そしてそれを分かるように説明しなければならない。練習もそうですけど、質問に応じることもそうですし、説明もそうですよね。そこに面白さを見出したんですね。
説明する、ということは予想外に難しかった。
──これは日本語らしい、これは日本語として正しいという判断が、私なりにできるわけですよね。でも、説明はとても難しいです。例えば、「は」と「が」の違いもそうですけど、初めから最後まで「は」と「が」の問題っていうのは、いろんな機能がありますからね。
しかしこの一年間の経験が、ICUで得た英語の技術と日本語教育への興味を、明確に結びつけたという。
──それまでなんのために英語を学んだかっていうことがね。特に大人の学習者を納得させるときの、仲介語としての英語の役割っていうのが、非常に大きいっていうことが実感として体験したわけですね。そこで初めて、私はICUの1年生で特訓を受けたフレッシュマンイングリッシュを、このように使うんだっていうことを、頭でなくて、体で理解した。ただ日本語を教えると同時にね、英語を使うことによって、うまく説明できるとかね、非常に、教育に対して英語を活用できるということにね、目覚めたわけです。
シニアフェローという新しく、また、他大学にはみられない制度を設け、上野氏たちを指導した小出教授について、上野氏はこう語る。
──先生の頭の中には、日本語教育のきちっとしたカリキュラムを学んだ、日本語教育の方法を学んだ人が、いつの日か教壇に立ってほしいというのが願いだったと思うんですよ。先生はいち早くね、受講した者を活用しようと思われたんだと思うんですね。だから、実習の場を、ご自分の監督下で1年の『Elementary Japanese』、教えさせてみようということを、すごいそれは決断だったと思うんです。
日本語教育の未来のためにチャンスを作ってくれた恩師の下で、上野氏は実際の指導を通して様々な経験をし、工夫を重ねた。
その後大学院へ進み、大学院生助手として教壇に立ちながら学ぶ道を選んだ。
そこで担当したのはICU日本語教育のメインであった『INTENSIVE JAPANESE』である。集中型の講座を受け持つ側になって、もちろんスケジュールはびっしり。それに加えて自身の修士論文、勉強と、大学院時代は本当に多忙だったという。
──もう本当に忙しかったんですが、院生助手の2年間『INTENSIVE JAPANESE』を担当したことと、その前のシニアフェローの1年間『Elementary Japanese』を担当したこと、これは本当に日本語の基礎文型に基づいた内容をこなすっていうことですよね。ですから、その部分と中級上級の部分を、あとの2年を通して、ほとんど全面を体験したっていうことですね。
自身の研究のために英語教育を学びながら日本語教育に携わった経験は、何事にも代え難いものとなった。
──本当にたくさんの時間を院生助手の時代には、日本語教育に使わせてもらったっていうか、そういうチャンスを与えていただいた。でも、これがその後の私の進路に、ものすごく大きく影響してるんですね。幸いにも、ほとんどの方が経験できないような、ゼロから出発した学習者を上級まで、大学の講義に対応できるような日本語能力のほとんどの部分を、院生助手のときに経験したんですね。この3年が将来の進路をですね、ほとんど位置付けたわけです。
渡米
大学院での教授経験を見込まれ、修了後は日本語研究室のフルタイムの助手として採用された。
──それだけの経験と基礎訓練を受けてるわけですよね。小出先生の目から見れば、大学でのきちっとした教授法の授業を受け、そして実際に教壇の経験もしてっていうようなことなので、望んでいらした形の若手がそこに誕生ということで。
上野氏はフルタイマーとして大学で働きながら、次のステップとして、小出教授に勧められたフルブライト奨学金の試験を受けた。
──私はなぜか今でもわかんないんですけど、私はたぶん受からない1人だと思っていたんですけど、それが受かったかたちになって、それで1学期だけの助手生活をしたあと、アメリカに行ったんですね。
アメリカからの支援を受けていたICUから修了生が奨学金を得て留学へ行くことは当時、誰もが喜ぶことだった。渡航費、生活費、授業料、全てを助成されるフルスカラシップで、一年間の留学。日本からは様々な分野の渡航者、特に省庁関係者や大企業の社員などの留学が多かったという。東南アジア出身のフルブライト奨学生も多く参加したハワイでの一月間のオリエンテーションでは様々な国の人々と出会った。
──ある意味では本当に分野様々ですね。目的はね、大学院留学なんですけどね、大学院で学位を取ることじゃないんです。これは友好のためなんですね。日米友好のためなんです。だから、1年で帰ってくるっていうのが大前提。でも私はね、初めからそういうふうに思ってないわけよ。
上野氏の目標は、博士号の取得だった。
──だって、修士終えたんだから、次は博士でしょ。奨学金も与えられて、期待も分かるわけですよ。なぜかと言うと、卒業生の中で、その時点で博士を持っている人は誰もいないわけです。もちろん日本語教育は誰もまだそういうことはないし、日本語教育の研究室の中で誰も学位は持ってなかったですから。
恩師である小出や大学からの暗黙の期待と、草創期のICU生としての責任感もあった。
──私たちICU生は、ICUは明日の大学っていうイメージをいつも持ってた。明日の大学、明日の大学って言ってた。まだ完成されてない。だから私たちが創らなきゃいけないんだっていうのがあったんですよ。
渡米した上野氏はミシガン大学に入学した。
懸命に学んだミシガン時代
ミシガン大学で専攻したのは言語学であった。
──留学前に日本語教育を通して、いろいろな母語の人に日本語を教えたわけですよね、3年間ね。そのときに思ったことは、言語の仕組みをしっかり捉えた、枠組みを知りたいっていう思い。それは日本語教育のメソッドとは全然別で、言葉の仕組みね、いろいろな言語がある、その全体を見られるような仕組みを、とにかく手にしたいっていうのがあったんですね。
直接的に日本語教育を専攻しなかった理由は、もう一つあったという。
──日本語教育は国際的な教育だから、日本でそれを掘り下げるという選択は、第一にはしないほうがいいと思った。海外から来ている異言語を持った、違った母語を持った人たちを迎える、違った母文化を持った人を迎える、そういう日本語教育をするには、日本だけを見るべきじゃないっていうのがあって。
言語学専攻のドクターコースに入ったが、ICUで学んだのは英語教育である。言語学の基礎を身につけたかった上野氏は、一年目でドクターコースの必修科目に加えて言語学の修士課程の科目を取り、二年目に修士号を取得した。
──それは忙しかったですよ。本当に。ミシガンのような所はね、留学生もいろいろな分野にたくさん来ていますから、留学生だからといって特別扱いしないです。だから1年目はですね、自分のアパートと図書館と教室を、3点だけですね、往復したのは。朝も4時頃から起きて、勉強して。
目の回るような一年を過ごした中でも、周りの人たちに救われたという。
──チーズケーキをね、一緒にお茶を、飲み物をなんていうようなね、とても親切な人がいて。チーズケーキなんか食べたことなかったんです、それまで、日本で。でも、とってもおいしいなと思ってね、おいしいって言うとまたね、誘ってくれたり。最初の1年は、本当に科目を処理するのに大変でしたけど、出会った人たちはとてもいい人たちが多くて。
アメリカでの研究生活では、アメリカナイズされていたICUと比べても、大きく異なる部分を感じていたという。
──やっぱり学び方の違いがありますよね。一つには、たくさん読まなきゃいけないっていうこと。それと、しょっちゅうペーパーを書かなくちゃいけない。何か提出物がある。それと、大学院の場合、セミナーがありますから、ディスカッションしなきゃいけない。ディスカッションするためには、事前の準備もいるし、言わなければいけないことを、タイミングをよく言わなきゃいけないわけですよ。ターンテイキングっていうね。だから、黙っている学生はだめなのよ、アメリカは。自分を主張していくっていうのが基本ですよね。それはね、日本でもトレーニングはなかったです。ICUでもなかったです。
量をこなすことと、自分を主張すること。この大きな二つが、大学院生活の根本だった。
──英語の使い方も、話し方も、人の接し方も、私にとっていいと思う現地のモデルに、絶えず生活の中では目を向けていた。というのはね、教えてくれる人はいないのよ。絶えず勉強でしたね。これはもう底がない、底知れないと思うんです。
日本語教育の骨子を成す言語学
生活や勉強、一つ一つのことを、全て自分で見て学んだ。そんな留学生活で、日本語教育に携わる機会はあったのだろうか。
──あったんです。本当に幸いに2年目のしょっぱなからね、院生助手として雇いたいって言ってくださったんですね。ミシガン大学に極東言語文化学科っていうのがあって、そこは日本学、日本語っていうのを勉強してるとこね。
ICUでの経験を買われ、ミシガン大学でも初級日本語を教えていたという。
──アメリカでも完全に丸2年教えたわけです。自分も成績を付けたりっていうことも、全部したわけですね。
アメリカでの日本語教育経験も積む中で、改めて上野氏は日本語教育を行うに際しての言語学の大切さを認識した。
──仕事としては日本語教育はすごく面白い。でも、その背後の研究はね、絶対おろそかにできないっていうのが、私がずっと思ってきたことなんですよ。言語学をきちっとしなければね、日本語教育はできない。
言語学の歴史の流れと、言語教育は密接に関係しているという。
──言語学の中身がね、だんだん変わっていくんですよ、のちのちはね。というのは、言語学も進展をするから。当時は構造をきちっとすることね。それからだんだん70年代ぐらいになると、パラダイムシフトがあって、言語学というのはコミュニケーションを目指さなくちゃいけない、ていうようなことになるんですけど。コミュニケーションを目指さなくちゃいけないっていう言語学のシフトっていうのはね、私はすごく素直に受け取れたの。というのはね、日本語教育をしてるから。そういう時代的な流れに、日本語教育の経験が呼応してるわけ。言語教育、習得の在り方を見ていると、今まではなるほどとは思わなかったこと、だけどなんか引っかかってたことが、言語理論の進展によって、ああ、なるほどって思えるようになって。
言語学と言語教育を突き詰めて考えた上野氏は、帰国後に東京大学で脳と言語の仕組みの研究まで取り組んだという。日本語教育のための背景としての言語学が、常に思考の中心だった。
出産・子育て・研究・教育
留学先で目標としていた博士論文は、三年間の留学で果たすことはできなかった。資格試験の途中で、止むを得ず帰国する必要が生じたからである。
──その帰ってきた理由というのは、夫が7年間アメリカで自分の研究、博士論文をやって、一度も日本に帰ってない、一度も日本に電話したことがない、できない。できないんですよ、その頃はね。そういうところに大学の教員ポストを。ルーテル学院大学なんですけど、自然科学の教授で帰ってこないかってお誘いがきたんですね。7年も帰っていない、電話もしてない。もうこれは帰ったほうがいいと。始めは私が残ってと思いましたけど、でも学位論文というのはそんなにすぐ書けるものじゃないから、私の意図としては一緒に日本に帰って日本で準備をしてというふうに思ったんですよ。
と〔1962年・東京都三鷹市〕-1024x572.jpg)
三年間の留学を経て帰国した上野氏は、専任助手として再びICUで働き始めた。助手という名前だが、専任教員として教壇に立ち、また教材開発も仕事だったという。
──帰ってきて63年から68年までいたんですけど、その5年間は本当に教材の改訂に明け暮れました。副教材を作ったりね。
一緒に作業をした講師たちは、そうそうたる面々が揃っている。北條淳子、奥津敬一郎、上野氏と同様に日本語教育の礎を作った面々が、ICUで切磋琢磨しながら共に働いていた。
五年間の専任職と並行して出産を経験し、子育てをしながら言語学論文執筆のための研究をした。
──実際の仕事は常に日本語教育でしたが、本当の専攻の分野というと言語学なわけですね。そうすると言語学理論の進展を常に身に付けていなきゃならないというのがあったわけですね。学位論文はアメリカで書くんだから、アメリカにおける言語学の大学における言語学理論の受け止め方にはついていかなくちゃいけないということで、それに日本にいた5年間、一番努力したんですね。
家族を持ち、再度の留学のための資金も貯めなければならない。自分の研究のみに集中していた学生時代とは大きく異なる環境になっても、上野氏は努力を怠らなかった。いつアメリカに戻っても良いように、下準備を整えておくことを自分との約束と決め、ICUでの日本語教育に力を注いだ。
──ICUにいるときは教育。ICUを出たら今度はうちのことを考える。だって子どもがまだ小さいですからね。家庭と専任職の場の仕事がほとんど時間を取りました。その間を縫って研究というか理論の進展を勉強。
先の見えない中で、それでも博士論文執筆の努力を続けた理由は何だったのか。
──最初(留学当初)帰ってくるときには当然博士号を持って帰ってこなくちゃいけないと思ったんですよ。だってそれだけの奨学金をいただくし、奨学金もいろんな人が欲しいと思ってるのをなんか宝くじみたいにいただいたわけですよ。だからそれは当然そうしなきゃいけないと思ったのに、途中で結婚して帰ってきたでしょう?しかもそれが夫の理由で帰ってきたということがあって、本当はもっとあと2年か3年いて終えて帰ってくるべきだった。
母校のためにチャンスを活かしきれなかったという気持ちが、何としても論文を書き上げにアメリカへ戻るという強い気持ちの原動力だった。
しかし、帰国してからの、ICUにいた5年間はまた実りのあるものだったという。教材開発に加え、教育助手としてICUで行われていた日本語教育のほぼ全てを手がけた。そして、コースで用いられる教材の改定作業がひと段落した時期に、ミシガン大学で講師として教えながら論文を書いてはどうかという話が舞い込んでくる。上野氏はそのポストを受け、渡米したのちに講師として働きながら3年間で論文を書き上げた。
帰国後の方針として、当時の上野氏はICUへ戻ることが当然だと思っていたという。
──母校以外で私は生涯を送るということは考えなかった、最初は。ちゃんと学位を持って帰って、そして日本語研究室、日本語科と言ってたかな、それの充実と後輩の指導、あるいは学生の教育に従事することが私の本当に将来設計だったんですよ。でもあるときに曲がったんですね、道が。
帰国して母校に戻った上野氏は、大学のシステムという思わぬ壁に直面した。評価されるべき成果をアメリカで挙げてきたものの、大学側は専任教員というポストを急に作るわけにはいかなかったのだ。そして上野氏の中で、もう一つの大きな理由が膨らみ始めていた。
──ポストがそのまますぐなかったということがあって。博士号を持っているのになんで助手なのかというようなことも周囲から問われたことがあるんですよ。また、研究をもっとしたいという気持ちはあったんですね。ちょうど博論が終わったときに、やっぱり一つの論文を終えたときっていっぱい残ったものがあるじゃないですか。こういうことをもっとしたいと。
ICUでの日本語教育は、5年間に既に手がけた。自分の研究をもっと深めたいという希望が強くなっていた。
東京大学での研究とアメリカでの夏期講座
上野氏は新しい環境で、研究に打ち込むことになる。研究助手のポストに空きがあると言われて移ったのは東京大学である。
──東大には研究助手のポストで入ったんですけど、すぐ講師になったんですね。そうすると今度は全部時間がリサーチなんですね。
思わぬ形で研究に没頭することができた。所属したのは音声言語医学研究施設という研究所だ。
──音声言語医学研究施設というのは物理学的と工学的な人とそれから医学的な人とそれから言語研究の人と、こういう学際的な研究の場だったんですね。いろんな実験的なことをするときには物理とか工学関係の技官の手も借りることができるんですよ。
多方面の専門家と共に研究するという恵まれた環境で、上野氏は音声と理解について研究し、本格的に科学的な分野まで分け入って論文を書いた。没頭できる研究を進めていても、上野氏はやはり日本語教育と無縁ではいられなかったという。
──アメリカのミドルベリーカレッジというところ。その学校は夏だけいろんな語学校が林立するんです。全米からこの学校に大学生が集まり、学びたい言語だけに集中する生活を数週間して、所属大学の一年分の学習を終えて帰るという。そこに私は4夏行ったんですよ。日本語学校はJapanese Onlyの10週間とか。
-1024x659.jpg)
上野氏はその夏期講座に、日本語講師として招へいされた。
──アメリカの日本語学校は大学生に教えるとこなんですけど、集まる先生方が全米から来るんですよ。やっぱりそれなりの経験のある人を求めているわけ。
旅費と滞在費はミドルベリー大学側が負担したため、上野氏は一人娘を連れて毎年教壇に立ちに行った。4年目の夏はディレクターも務めた。
──娘だけ連れてその期間行って、私のためにはアメリカの日本語教育の全貌を夏の期間で見る。それからもう一つは言語学会というのが、全米のサマーミーティングというのがちょうど7月から8月の頃にどこかであるんですよ。それになるべく出る。そうすると学会の動向も知ることができますよね。いろんな人にも会える。
日本語教師としての経験のため、という理由も大きかったが、もう一つの大きな理由は娘の英語教育のためでもあった。上野氏の二度目の留学と共に現地の学校へ通っていた娘は、4歳から7歳を英語環境で過ごした。日本へ帰国してからはひたすら日本語への適応を目指した。
──その間に娘が英語でしたことは常に読むことなんですね。だから英語の本を読んで、出かける時も持っていって読むわけですよ。ところが話すことは日本に戻って1年ぐらいたったらできなくなったんです。つまりスピーキングとリーディングの頭の作用は違うんですね。だからスピーキングは使ってなきゃ駄目。
そんな時にミドルベリーへの招へいを受けた。
──私は夏だけでもRe-exposureというかもう一度英語圏で英語で学習したような環境に戻してみたらどうかなと思って。そしたら面白い現象がね。着いた1週間は沈黙。サイレントピリオドというのがあって、そのあとはヒュッと、もう全然私たちの英語じゃない、ネイティブのような英語になるんですよ。
上野氏は娘の英語力を失わせないためにも、夏になるとアメリカへ渡ったという。親子で時間を共有した夏は、娘が中学生になるまでの4年間、毎年続いた。
国立国語研究所での奮闘
東大で6年間勤務した上野氏は、再び日本語教育に携わるべく1977年に国立国語研究所の日本語教育センターへ移ることになる。当時発足したてだった日本語教育センターは、人事的に未整備だったという。
──日本語教育を実際にやったことがある方で名前があったのは水谷修さんだけ。そのときには本当に「え、この人がどうして日本語教育?」という方の名前しかなかったんですよ。また研究室もまだ人が埋まってなかった。
上野氏は奮起する。
──とにかくこの人事では日本に唯一の、そしてこの時期にしか始まらなかったセンターとしては非常に不揃いだと思ったんですね。それで生まれて初めて自分からポストに応募したんですよ。というのは、おこがましいんだけど、こんな人事では私は駄目だと思ったんですね。
実際に入ってみた国立国語研究所で、上野氏は認識の違いを見ることになった。
──国語研というのはやはり国語研究、国語ですからね、日本語でもないんですよ。だからやっぱり近代の日本語から現代に至ることを扱っているんだけど、やっぱり国語的な頭で日本語に向かってるわけですよね。でも私は日本語教育の日本語は世界の言語の一つとしての日本語でなくちゃ駄目だと思っててね。国語という概念は取っ払わなくちゃいけないと思ったんですよ。
上野氏は国立国語研究所で、女性研究者として当時異例の室長に任命された。そこで上野氏は改めて、国立国語研究所が日本国民を相手にして言語文化をどうするかということと、言語資料をどうするかということと、そして、日本語教育センターをどうするかということとは、やはり違っているべきだと考えたという。
──日本語教育センターは本当に世界を相手にする場だから、ということがまずあったんです。中に入ったら(みんな)全然そういう志はない。だからそれを入ってから確認して、ものすごく私は努力したんですね。だからそれからの人事は、世界に通用するような研さんを積んだ人に焦点をあてました。
周囲からは、「何を言い出すかわからない」と言われたというが、自分のためにしているのではない。
──日本語教育のためにそう考えざるを得ないですよ。だってそう考える人がいない。だから必要なときにはね、声を大にして特に誰を次のメンバーにするかとか、そういうときに大事ですよね。やっぱりどういう経験とどういう研さんを積んだ人がその組織のメンバーになるかによって将来が決まりますよね。だからそれは、私は本当に去るまで努力をしましたね。
日本語教育にとって大切なのは、真の国際的思考ができる人物だという。国内だけにとどまらず、国外に目を向けられる能力を持ちつつ、地域性を理解する人。そのために必要なのはやはり経験だ。また、学位を持っているかという点にも重きを置いた。
──学位を取るということはそんなに易しいことじゃない。3年か4年かかかって何かをきちっと調査なりなんなりして、そこからいろいろ自分なりの考えを出して新しい貢献ができるようなそういう成果を出すわけでしょう?それをしてるか、してないかというのは全然私は違うと思うんですね。
そうやって集めていったメンバーは、自然と女性が多くなったという。
──海外で日本語教育に関係してるところで働いている人たち、女性が多いんですよ。男性にとっては非常に不安定な仕事なのかもしれない。
道筋の出来上がっていなかった日本語教育という分野を、上野氏は国立国語研究所日本語教育センター第二研究室というフィールドから懸命に整備していった。その後、数々の部長を排出し、花形となっていく第二研究室で奮闘し続けた上野氏は、「男なんぞに負けるな」という祖母の言葉をまさに体現していたと言える。
日本語教育のための核として
国立国語研究所で新しい挑戦をスタートさせた上野氏は、当時の体制をこう振り返る。
──個人的にはみんなとてもいい研究者がそろっていますけど、組織としてはやっぱり私は「古き革袋に新しき酒」って思いましたね。
良い経験を積んだ人材を集めても、研究所自体の古い体制に苦い思いをすることは多々あったという。また、当時圧倒的に日本語教育経験者が不足していたために、日本語教育センター内で分担されていた様々な研究や研修にも次々に駆り出された。
上野氏が携わった大きなプロジェクトとして、年少者教育がある。この年少者教育ができる教員を研修、育成することが、プロジェクトのゴールである。これを受け持った上野氏は、まず大学レベルで設置されていた日本語教育の教育研究協議会に声をかけた。当時の教育研究協議会はほぼ各大学にあったにも関わらず、横の連携が全くない。言わば一城の主たちばかりだったという。大きな組織であった筑波大学、名古屋大学、広島大学の三校の教員を幹部として、その他全ての国立大学に声をかけた。いくつかの大学から国立国語研究所へ教員を集め、会議を行ってみた。
──初はみんなそれぞれ沈黙。「自分のところで何をしてますか?」ということを発表していただいて、「何が問題でしょうか、どういうふうにそれを解決されましたか?」ということをやっていって。1年目は沈黙ね。2年目に少し意見の交換ができる。3年目はお互いに何かやりましょうということになって、それで初めて一城の主が手を組むわけよ。
各校から意見が出始めて、ようやくプロジェクトは軌道に乗り始める。教材が無い、教員を養成する技術が無い、不足している点や問題点が次々に具体化されていった。同時に、当時の中曽根首相が打ち出した留学生10万人構想を皮切りにして、教員養成が急務となる。それは日本語教育センターの研修ノウハウを活かす場となった。かつてICUが担っていたものを、国家規模で担ったのが日本語教育センターだったのである。
──そういう意味では日本語教育センターは国の留学生受け入れのための教員の核ということかな。
この取り組みは高く評価された。しかし、同時に国立国語研究所の威光を笠に着ることは、あってはならなかったと上野氏は言う。
──私、よく言ったのね、研究所の人にね。「研究所で働いていて、いろんないい先生が来てくださるのは決してわれわれがどうしたからじゃないんですよ」と。「みんなの能力も、それはみんな能力持ってるけれど、国語研にいるから、その能力が評価されて使われるんですよ」って。だからあんまり自分たちで全部うまくいったと思うのは、ちょっとそれは間違いじゃないかということをときどき言いましたけどね。やっぱり所属してるところの持ってる力というの、あるのよ。
それを踏まえた上で、上野氏は自分のできることとして人事をやり切ったと振り返る。
──日本語教育センターが活動していた期間というのは国の中心の機能を果たしていたと思いますね。最初は本当にメンバーも少なかったけど、私が去ったのは14年目ぐらいなんですけど、そこでほとんどの人事が終わったんですね。私が去るときには後ろ髪を引かれませんでしたね。ちゃんと引き継ぐ人が立派にいるって感じでした。
国立の研究所という大きく一筋縄ではいかない機関へ飛び込み、日本語教育の環境整備に取り組んだ上野氏は、戦後日本語教育の成長期の中で、日本語教育に携わる人々がつながり協働する重要な場の構築を担ったのだ。
人材育成
「日本語教育は変化をよく見せてくれる」という点にも、上野氏は魅力を感じるという。先述した中曽根首相の留学生10万人構想にもあるような国家的な戦略は、必ず対外関係に深く関わっている。
──他の先進国がこれだけ受け入れているのに、日本はどうなんだというようなことが背後にあって、首相の方針が出されるわけですよね。日本の国内の出来事に終わらない。
日本語を教えるということは、国内に目を向けていることではなく、実は他の教育よりもずっと、外へ向いているものなのである。
──そこが私は日本語教育のすごく面白いとこだと思う。対日本人だとね、例えば英語教育に関わると職も相対的にはいつもあるし、実入りも悪くないと思うのね。でも日本語教育のようないろいろな変容に富んだ内容にはならないですよね。そういうところは私、日本語教育というのは本当にいろいろな国とのつながりで内容が構成されますよね。もちろんそれは教えるときにもだし、受け入れるときにもだし、海外に行ってもそうですけどね。海外に行って教えてる方は本当にその国に適応しなきゃいけないし、その国で教育成果を上げるための工夫が随分いると思うんですけどね。そういう点がとても面白い側面を持ってるんじゃないかなと思って。だからそういう意味では今振り返ってみて「ああ、面白いところに立ったな」と思いますね。
国立国語研究所を退任した後、上野氏は東京女子大学へ研究の拠点を移し、人材育成に取り組んだ。その間、文部省学術審議会専門委員、国語審議会委員、国際交流基金運営審議会委員、日本語教育振興協会審査委員会委員、国際文化フォーラム評議員、言語文化研究所評議員、国際日本語教育普及協会評議員、日本語教育学会監事、外務省外部評価委員会委員、特定非営利活動法人日本語教育研究所理事長などを歴任した。全てに共通することは、人材や後進の育成である。
──人は自分が育つのに精いっぱいな時期ってあるわけですよね、若いときはね。でもやっぱり人材育成というのは、常に私には後輩がいたんですよ。つまりICUも私たちが最初の助手になったように、最初の日本語教育の訓練を受けた者ではあったんだけど、すぐ後輩がいたわけですね。そうすると一緒に働いてると人材育成というのは全てのときにあるのね。国立国語研究所の場合は特に去るときに後ろ髪を引かれる思いはなかったと言ったぐらいに、いい人材が職員としていたということですよね。もちろんいろいろなプロジェクトの中で学習者を育てるということ、これはもちろんですけど、職場の人材育成ってことも大事だと思うんですね。
特に大学において教員間で相互に高め合うということは、忘れられがちだという。大学の目的が学生を育成することだけに着目されがちで、教員間で各々を育て合うということは意識されることが少ない。そこで、他機関で育て合いが可能になる場をつくることも大切だと言う。国立国語研究所で上野氏が取り組んだように、日本語教育に携わる者たちが、相互に惜しみなく与え合うという場や意識が今後の日本語教育の展開にも不可欠であるというのだ。
──共同研究をするとかそれも一つだし、その中でやっぱり育てることもできるし、育ててもらうこともできますよね。だから人材育成というのは自分も含めて人からいろんなものを受けることも自分の育成だし、それからそういうものを分かち合うことも互いの育成の道だと思うんですね。それはもう惜しんだら駄目だと思うんです。
自分の視野の中に閉じこもらず、外の世界に目を向け、時に自分の成果を分かち合うことが欠かせないというのだ。なぜ、上野氏は、こうした考えに至ったのだろうか。
──というのは本当に自分ができることというのはほんの一部だということを痛感してるんですよ。だからわずかなことでもいい加減にはできない。わずかなことを自分なりに、もししっかりしたとしたらそれがもう少し大きい部分の一部になって、自分はできなかったけれども、ほかの方がやった成果と合わせてみて、こういうふうなこの研究の位置付けと、それからこういうふうな全体の様相が見えてくるということが体験できていったらいいかなと。いいかなというか、私はそれが大事だなと思いましたね。
人と人との関係や連携を重視した上野氏の人生。その歩みの中で、日本語教育はどのような意味を持つといえるのだろうか。
──日本語を本当に私なりにですけど、たぶんほかのことをしていたら見なかったであろうように、客観的に眺めることができたと思います。日本語という点では、自分を何で伝えるかというと、もちろんいろんな伝え方あるけど、言語なしには伝えられませんよね。そういう意味で日本語が自分自身だとしたら、その自分自身をより客観的に見る、そういう手だてを日本語教育という仕事に携わったことでより深く、それから常にチャレンジとしてそれを見ることができたと思います。それはたぶんそんなことは考えてもみなかった、最初は。
日本語を通して自分自身を知り、そして異言語を話す人々に教える仕事を持ったことで、彼らと彼らの言葉や文化への理解も深まった。そしてその理解は、日本人としての自らの理解にも役立った。
英語教育の花形であったICUで学び、当時日の当たらない道とされた日本語教育を選んだ上野氏は、自分が歩んだ道のりをこう振り返る。
──貫く、継続するっていうことの、忍耐というか、そういうね、性格はあるんですよ。私は花より実を取りますっていうことで。世の中がね、英語教育を花と見ても、私はやっぱり自分が本当にいいと思うものを取るんだって。まあ、やりたいことをやったんでしょ。
最後に、上野氏はすっぱりとこう言った。
──道は一つしかないのよ。二つを同時にはない。こっちを行って、こっちを行って、どっちがよかったなんてないんですよ。常に道は1本しかない。その道を選んだら、それで勝負をするしかない。
ICUに学び、アメリカで研究し、その豊かな経験と知見を以って日本語教育の基盤構築と人材育成を果たした上野氏の道が、そこには確かにあった。