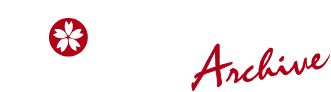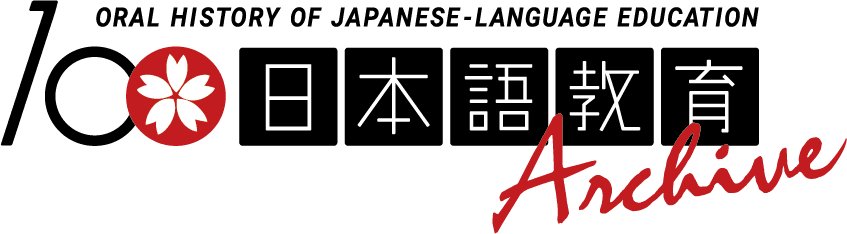01
SHUHEI SOEDA
日本語放送に捧げた五十年
添田修平 Shuhei Soeda
1929年神奈川県大磯町生まれ。1952年東北帝国大学(現東北大学)経済学部卒。早稲田大学大学院文学研究科修了(ロシア文学)。日本電波ニュース社に勤務後、1963年に妻である内海博子と共に渡中し、北京放送局(現中国国際放送局)入局。日本語部に所属し戦後日本から招聘された最初の局員としてそれぞれ趙志行、葉静の名を用い夫妻でアナウンサーを務める。外国人専門家としての長年の功績が認められ、1986年12月に中国政府より永住権を与えられる。1989年9月には李鵬中国国務院総理(当時)より栄誉証書が授与された。2002年に退職。
日本語放送 Radio broadcast in Japanese
日本国外から配信される日本語による国際放送を指す。1942 年に放送開始となったVoice of America(アメリカ)、Radio Moscow(ソビエト連邦)、1943 年放送開始のBible Voice Broadcasting(イギリス)の他、複数の国や地域による放送がある。BCL(Broadcasting Listening)ブームが起こったり、「北京放送を聞く会」等の組織的なリスナー活動が生まれたりしたケースが見られ、文化理解に大きな役割を果たした。
北京放送 Radio China International
中国国際広播電台による放送の通称。中国の放送事業は国務院直属の中央広播事業局が統括する。北京放送は海外向けラジオ放送で、中国国際広播電台が世界各地域に向けて放送を行っている。中国国際広播電台は1941年に設立され、国際放送は1950年に開始された。現在は英語や日本語、ドイツ語やフランス語、アラビア語、エスペラント語など43言語で放送が行われている。
世界を自分の目で確かめてみたい
日中国交回復前に中国へ渡り、中国国際放送局において現地ニュースを日本語で伝えながらアナウンス人材育成に力を注いだ添田氏は、神奈川県の大磯町国府村に、6人兄弟の末っ子として生まれた。
──6人兄弟の一番下ですから、どうせ外で生活するんで、長男で家の跡を継ぐわけじゃないから、『好きなことをやっていいよ』と、両親がそういう形で育てたわけです。だから、自分の好きなことで世界に。当時は日本でもやっぱり、海外にどーっと向かっていたんですね、青少年時代。だから、いろいろ本を読んだり、人の話を聞いたりして、日本の国内でね、生活が終わるのはやっぱり満足できない。『よーし、世界に飛び込んでいって、いろいろ体験して、知らないものを見てみたい』というね。こういういわゆる単純な海外志向の気持ちがだんだん湧いてきて。

1949年10月1日。東北大学に在学していた添田氏は中華人民共和国の産声を聞き、アジアの新しい社会主義国に強い興味を持った。
──新しい国がすぐ隣にできたんだな。古い中国はもちろんあるけど、非常に遅れた封建主義の強い国だと書物や人の話でわかっていた。蒋介石や何かが指導しているね。ところがこれがひっくり返って、新興の新しい国ができたなということで、すごく関心を持って、『一度自分の目で見てみたい』と、こういう動機ができたわけですね。
夫人と共に中国へ
世界は変わっていく。当時の仲間たちと募らせたその興味は、仕事へとつながっていた。
大学院修了後に日本電波ニュース社に就職。主にアジアの新社会主義国の情報を専門に収集し、日本に紹介する通信社である。2、3年すると、北京放送局から中国社会主義研究会を経由して、日本語のできる人材を探しているという話が来た。契約は3年間だ。

──新興の国々。新しく国づくりをしている国。国づくりですよ。そこのところでどんな国づくりをするのか見たいことと、その将来に対する希望というか憧れとこういうものが。若者ですから頭の中で合わさって。『じゃ俺行ってくるよ』といってね、簡単に承知して。
添田氏は一も二もなく承諾した。
〔1963年・神奈川県大磯町〕-1024x804.jpg)
しかし当時は国交回復前である。外務省は個人にビザを発給しない。そこで日中文化交流協会が外務省へ掛け合った。
──学習をするということと、交流の仕事をするということで、公に行くわけで、個人でもって勝手に行くわけじゃないから、ビザを発給してほしいと、こういう趣旨で外務省と長いこと接触して、交渉して、やっとビザが下りたんです。だからちょっとね、あれすると、おそらく外務省で公式の中国に渡航するビザが下りたのは、私は大変初期にあたるんじゃないかと。数少ない中の1人じゃないかと思っていますがね。
半年にも及ぶ交渉の末ビザを手に入れ、妻を伴ってノルウェーの商船で上海へ渡った。出発のときは、家族や友人が総出で見送ってくれたという。船と港、出航のときに紙テープを投げて見送りを受けた。当時の写真は今でも手元に残している大切なものだ。

初めて自分の目で見た中国の大地は、50年たった今でも目の前に蘇るという。
──胸がドキドキして。そのうちに見えてくると、唐家璇さんたちが『中日友好両国人民の戦闘団結万歳』という大きい横断幕を持ってね。これは一生忘れないですね。
若い添田氏の胸には思い描く夢があり、非常に気持ちが高ぶっていたことをはっきりと覚えているという。
上海で一泊した後、飛行機で北京へ降り立った。中国からの招待でやって来た添田氏は、国賓である。下にも置かないもてなしを受け、友誼賓館に半年間滞在した。
現代日本語と専門的なアナウンス技術を活かして
友誼賓館には国賓レベルの研究者たちや日中友好に尽力した様々な人物が滞在する。添田氏はそれらの人々と日々を過ごした。

北京へ来てから数ヶ月間、受け持った仕事は北京週報の日本語記事の添削だった。
──内心は『俺はこんな仕事をするためにやって来たんじゃない、俺は放送局でアナウンスの仕事をしたい。半年もこんなに毎日やって』と、正直なところ、不服があったんですよ。
そもそも契約時に約束されていた仕事は、北京放送局での対外放送のアナウンサーである。しかし、当時はまだ外交関係が成立していなかったため、直ぐに許可が下りなかったのだという。
名目上、添削の仕事を半年ほど続けた頃、北京放送局の外国人専家楼に部屋の空きが出た。放送局にも程近い立地で、世界各国から集められた様々な専門家たちが暮らす宿舎である。添田夫妻はそちらへ移り、各国の専門家たちとの交流を深めながら放送局での仕事を始めた。
専家楼には戦前からアナウンサーとして活躍した日本人も数名いたが、日本の現状も、戦後日本の日本語も知らない世代だったという。それに比べ、添田氏は若い。加えて通信社時代にアナウンサーとしての研修も受けている。やっと自分の知識や技術を活かせる場に来たという思いだった。
──こちらに来て、やっと本場のところでもってアナウンスの仕事も落ち着いてできるようになったなということで、自分では嬉しかったです。やっと本場でもって活躍できるなと思って。
録音から放送まで
日本と中国との友好につながる国際放送のアナウンサーとしての責任を感じ、マイクの前では常に緊張もした。
──自分の仕事が日本と中国の友好の懸け橋になるんだという、こういう自覚と思想はきちっとしていましたけども、第一声は非常になんとなくね、マイクの前にスタジオに向かったときにはね、やっぱり緊張していました。
出勤すると、一日に放送する中国国内の様々な出来事がリストにして渡される。それを少しデモンストレーションしてから、録音が始まる。当時は全て録音放送で、生放送は無かったという。
放送原稿は、まず中国人スタッフが新華通訊社から届いた中国語の記事を日本語に翻訳し、それを日本人スタッフが添削。そしてニュース原稿として添田氏たちの手に渡るという仕組みだった。下読みをして違和感を覚えると、添田氏が直接翻訳室へ行って直しを入れた。
──文章語とおしゃべり語と違いますからね。聞いてわからなきゃしょうがない。同音異義語というのがあるでしょ。音は同じだけど、意味が違う。だからアナウンスはなかなか厄介ですよね。下ごしらえをしてね。自分で声を出して朗読をしてみて。
原稿が完成するとそれを録音。そしてその音源を、また日本語の分かる中国人スタッフが間違っていないかをチェックする。そこまでの手順を踏んで初めて、その録音音声が電波に乗るのである。
中国のニュースを世界に発信するための放送。日本語で放送することで、日本に中国の情報が届きやすくなる。また、中国国内の日本語学習者も北京放送の熱烈なリスナーだったという。

──手紙がよく来ました。学生やなにか民間人もね、日本語の学習熱が中国でも盛んになって来たからね、一番手っ取り早いのは北京放送の日本語を聞いたら学習できるということで。それについての感想の手紙がしょっちゅう。
そのうち、リスナーからの手紙を紹介する番組を作った。このコーナーはリスナーからとても喜ばれたという。
困難の時代を乗り越えて
中国での3年間の契約期間が終わりに近づき、添田氏は妻と帰国しようと話していた。ちょうどそのとき、文化大革命(以下、文革)が始まった。
──66年から文革10年間で、76年くらいまででしょ。改革開放が、鄧小平が77、8年。ちょうどその境にぶつかったわけですよ。中国は今、国内が乱れているわけです。人事のほうも。特に放送の面ではやはり。文章を書いた、何をしたとかっていうことで、皆、精神的に中国人は不安定な様子。アナウンスを落ち着いてできる人っていうのは非常に少なかった。
中国人ですら、生き抜くのが難しい時代である。日本人である添田氏も、その波にもまれた。当時一緒に働いていた日本人や専家楼の研究者たちはほとんどが日本へ帰って行ったという。それでも残って放送を続けたのは、落ち着いて放送できる自らが続けなければという責任感からだったのか。
──それともうひとつ。国務院のいわゆる偉いさんが、当時、唐山地震がありましたね。あの前後辺りに放送局の放送のほうは安全かどうかって調査に来たりして。『あなた日本の専門家ですか、ご苦労様です。できたら今、もし放送に事故が起きたら世界的な情報の影響がありますから、あなたがた、ご苦労様でも残って放送を。特にアナウンスの仕事ですから、残ってやってください』と。『翻訳の原稿のほうは華僑が日本から帰って来たんで残っていてできますから。でもアナウンスはいないんです』と。『ですからあなたがた夫婦は残って放送したら』ということを個人的に、慰問に見えたときに部屋の中でそういうことを言われて。そういうことが非常に深刻に残っていたわけです。だから女房と帰りたかったけどね、やっぱりね、上から中央からのね。
どんな困難があっても最後まで残ってやり抜こうと、そのときに決めた。
アナウンス人材の育成
添田氏はアナウンサーの養成にも取り組んだ。若手アナウンサーを対象に、発音やアクセントの指導をするのである。これには、日本電波ニュース社時代に東京アナウンスアカデミーで訓練を受けた経験が役立ったという。
──本格的にアナウンスの勉強。体のほうからね。呼吸の仕方から始めましたから。
研修生たちはみな、名だたる大学の日本語科を卒業していて、日本語は達者だった。呼吸の仕方から変える、きれいな発音を教え、アナウンサーとして働けるように指導を繰り返した。
放送局では、アナウンスに関しても外国人専門家に頼り切るのではなく、中国の人材が活躍できるよう注力されていた。そのため、添田氏はアナウンス業の傍ら、中国人の人材育成にも積極的に携わった。しかし、教え子たちは当初放送局に居つかなかった。
〔1980年・中国北京市〕-1024x709.jpg)
── 一時はその頃、日本ブームがあって、日本に留学したいとか、日本で就職したいとかということで、みんな放送局に日本語の勉強に来る。目的は放送局の就職でなくて、日本に早く行きたいんですよ。日本語をしっかり身に付けたいという目的で来るわけです。みんな、3年契約たつと日本に行っちゃうわけです。
その現状に、添田氏は憤っていたという。
──『せっかく養成したのに、もう俺やだよ、もうこんな仕事』『だって日本にみんな行って、帰って来ないじゃない』って。『日本に送るための仕事をやっているみたいなもんだよ』って、上の指導者に文句を言ったりして。『だけど添田さん、ひとつ辛抱してやってくださいね。しょうがありません、私たちもどうこうできないんだから』って言ってね。そんな時期もありましたね。日本ブームですね。
放送局では、日本語を学んだ人材たちが実際に日本へ行き、日本人の中で生活や仕事をする。その過程で正確な会話力を身につけるという体験が大切だと考えられていたという。それらの体験を放送局へ持ち帰って初めて、完璧に仕事ができるようになる。
──こうなると一番いいんだけれどもという、そういうことですね。これは今でも変わりないと思いますけどね。
しかし日本へ渡ったきり帰って来ないケースの方が多かった。
──戻って来ないんだよね。『なんだ、俺たちの仕事は中国の人材を、日本に送り出す養成の仕事なのか』ってね。
アナウンサーとしての生活
アナウンサー生活で印象深いのは、様々な放送の中で、何よりもニュースが一番大切であるということだ。
──毛沢東や中央の指導者の会見や談話のニュースが入ってくると、夜中何時でも明け方でも飛び起きていって、起こされてね、スタジオに行ってそれを録音して。日本に翌日の朝ね、5時半から6時半まで30分間、日本語放送、朝特別あったんです。
放送局は24時間体制。大きなニュースには時間は関係無かった。
──『周恩来がこういう、日本の田中角栄のニュースが入ったから急いで出勤してください』って。電話が夜中に掛かってくる。行って、朝5時半のニュースに間に合わせて出すと、そういう生活でした。これが一番印象に残って、忘れられないですね。これは文革中もずっと続けましたからね、放送を。
1970年代には周総理にも会った。
──文革の末期ですね。外国人のいる専門家全部集めて、周総理がサンパチ、3月8日の国際婦人デーを開いてくれたんです。うちの女房やなにかも招待されて、そのとき特別なアレでね、家族も全部招待状が来たわけ。国務院から。人民大会堂で周総理の話を聞いて、簡単なお茶とお菓子の食事。そのときに周総理が来て、最後に全部家族にまで会って、うちの子供を息子と娘も初めて周総理と。
握手の力がとても強かった印象が残っているという。
──ええ、特徴がありましたね。普通は握手というのは『ニーハオ、こんにちは』と言ってあれです。でも、周総理はウッと握ってね、『本当にあなたと一緒なんだよ』と、『頑張ってやっていきましょう』っていうように。いつまでも忘れられないですね、あの力強い握手の仕方はね。
そんな周総理が亡くなったときも、添田氏はもちろんニュースを読んだ。周総理、毛主席、また唐山での大地震、様々な大きなニュースが、放送局に勤める添田氏の元にはいち早く入ってくる。いつものにぎやかな放送局とは違った、シーンとした雰囲気の中、一大事を告げるために放送の準備をする。
──周総理が亡くなったときは、原稿を作るところの翻訳部のほうに連絡が。そしたらすぐアナウンスの部屋のほうにも連絡が。そこで内部の通達があるわけ。こういうことで周総理が午前何時に亡くなられたと。
お悔やみの放送をして、涙が止まらなかったという。
唐山で起こった大地震のときも、非常事態の中でアナウンスを続けた。住んでいた専家楼も激しく揺れ、被害が出た。意気消沈する放送局員を、添田氏の妻が励まし続けたことが印象的だったという。
五十年の歩みを振り返り今思うこと
中国の激動の時代を日本語放送を通じて伝えてきた添田氏は現在、北京での生活が50年を超え、日本で過ごした時間よりも長くなった。中国へ渡ってから40年余り続けたアナウンスの仕事を退職し、国家から手厚い生活の保護を受けながら穏やかに暮らしている。
長いアナウンサー生活の中で、記憶に残っているエピソードを話してくれた。
──そうですね、ひとつはあの原子爆弾。アメリカが第一でしたかね、ソ連が第一でしたかね。どちらかが原子爆弾を開発して、そのあと二番目か三番目に中国で初めて砂漠で原子爆弾の実験をして、実験に成功した。このニュースを日本向けに出す、読むということが、やっぱり非常に複雑でしたね。
また、毛沢東主席逝去の知らせも、印象深いという。
──もう、第一に日本語部のね、職場がね、もうみんなぼろぼろ涙をこぼしてね、仕事もできないわけですよ。自分の机に座ってね、『ふんふんふん(嗚咽)』とやっていてね、もうお互いのおしゃべりができない。こういう雰囲気ですね。それほどね、やっぱり毛沢東主席の亡くなったときの影響っていうのは、中国の一般の人たちに対して、すごい影響力があったんだなということがわかりましたね。ちょうど自分の両親や肉親が亡くなったときにね、家族に対して思い出でもって泣くと同じような感情でしょうね、職場が。
添田氏自身も、声が震えるのを抑えられなかった。とはいえアナウンサーとして震えた声での録音はできない。何度も原稿を読み直した思い出があるという。
また、毎年国家から招待された春節のお祝いは、国家の要人が集まる中で盛大に祝い、食事をする華やかな場だったと語る。
──幸いなことに当時はね、中国の風俗・習慣として、『好客(お客さんをもてなすことが好き)』というんですかね、お客さんをだいじにする思想が下までずっと貫いていたわけですね。中央の最高の指導者、それからあと大臣、それから対外関係ですね。われわれ外国人ですから、外国人と仕事で接触のある機関の幹部や指導者、みんな寄って。ですから、人民大会堂ももう1,000人、2,000人近くの大変な宴会ですよ。
初めは3年間の約束で日本を離れ、半世紀を超えた。中国の時代の波にのまれ、国家からの要請で中国にとどまり、「意義のあることだから最後まで頑張ろう」と夫婦で時代を乗り越えた。アナウンサーを続ける傍ら、中国人の若手を育てることにも力を入れた。日本語の発音、話し方、雰囲気、そういうものを伝えるために、妻と工夫して教材を作り、養成をし続けた。長きにわたる中国生活を振り返って、添田氏はこう語る。
──何というんですか、言いづらいんですけどもね、自分自身は大変満足しています。やっぱりね、自分の人生をね、思い通りにね、まっしぐらに進んでやってきて、もう80代の老年に達したと。ということで、自分の人生に大変満足を感じています。で、日本と中国の友好のために、少しでも役に立ったと、自分の人生がね。ですから、そういうことで、大変満足感と安心感というかね、そういうあれがあります。
そして今の時代を生きる若い人たちに向けて、こう話してくれた。
──やっぱり一言ね、自分の思った信念ですね、信念をね、やっぱり最後まで貫き通すというね、『よーし、やってくぞ』というね、こういう覚悟というか、決意というかね、これがやっぱりないと、物ごとがね、やっぱり思う通りにはできない。そういう考え方、思想をきちっと自分に持つことが大事だなということです。これは自分の2人の子どもにもね、いろいろおしゃべりをしている中で伝えています。自分の人生観の一つとして。
覚悟を決めて自分の人生を生きる。その姿勢が、どの時代を生き抜くにも何より大切であることを、添田氏の人生が強く物語っていた。